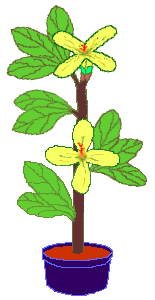
最終章 二つの山
いらいらしながら、それでもじっと待っていると、どういうわけか理沙の母が姿をみせた。キョロキョロしながら自習室全体を見渡していた。
(理沙を捜しているのか?)
母が図書館にくるなどと、理沙には聞いたことがなかったし、主婦が図書館に用があるとも思えなかった。良次は立ち上がり、理沙はまだきていないことを教えてやるつもりで近づいていった。
良次がカウンターのところまでいくと、やっと理沙の母は気がつきニコッとした。
「こんにちは」
以前会ったときのような、いいとこの奥さんといった優雅さは見られず、ひどくそわそわしていた。
「その節はいろいろめんどうかけました。理沙さんはまだきてないようですよ」
「いえ、あなたを捜してたんです。よくこの図書館で逢ってるって聞いてたものですから」
「はあ、僕をですか?」
「ちょっと理沙のことで話しがあるんです。どこかその辺の喫茶店にでも入りましょう」
「そ、そうですか。じゃそちらに食堂がありますから、そこにいきましょう」
容易ならざる理沙の母の様子に、歩くのももどかしく駆けるようにして席に戻り机をかたずけると、理沙の母を案内して食堂へ入った。
「実はおとといの夜、七時過ぎぐらいだったんですけど、帰宅途中に家のすぐ近くの公園で・・」
理沙の母はそこまで言うと、コップの水を飲み深呼吸をしてから言葉を続けた。「変な男に襲われてしまって」
「ええっ!」
唖然として次の言葉を見失った。
「通りがかりの人が助けてはくれたんですけど、制服はボロボロになるやら顔や手足に傷を負ってしまうやらで、どうしたらいいのか。警察に言うわけにもいかないし、あなたにも傷が治るまでは黙っていようと思ったんですけど、隠し通せるわけでもないでしょう。理沙もあなたには絶対教えるなって言うんですけどね」
理沙の母は一息ついて、ハンドバッグからハンカチを取り出すと目許を拭った。
「すみません、僕のせいです。僕が家の前まで送っていかなかったからです」
理沙とはおとといの日も図書館で勉強したあと、理沙の家の近くまでいって軽い食事をして別れた。それが、やはり七時ぐらいだった。理沙の家は国道から小道を入り、百メートルほどいったところの住宅街の一角にあった。古くから住宅街の広がったところではあるが、理沙の家の周りだけは、もともと沼地だったところを埋め立てて整地した造成地の中で、まだ空き地が目立つような場所だった。
家の前まで送っていったのは、最初の二、三度だけで、あとは理沙も近所の人に見られたりするし、そこまでは必要ないというので、いつも国道のところで別れていた。
「じゃ、おとといの日もいっしょだったんですね」
声を出す元気もなくなり、黙ってこっくり頷いた。「そう。別にあなたの責任じゃないから気にしないでください。それより理沙に会ってくれませんか。元気づけてやってほしいんです」
「はい、これからいきます。あの、それで」
口まで出かかった言葉を慌てて呑み込んだ。
「ええ、ありがとう。ただ良次君にも誰にも会いたくないって言って、食事も満足にしてないんです。直接いけば変わるかもしれませんから」
「そうなんですか。とにかくいきましょう」
いてもたってもいられず、理沙の母を急き立てるようにして席を立った。
自転車は図書館に置きっぱなしにしたまま、二人でタクシーに乗って病院へ駆けつけた。病院特有の匂いは、良次の重苦しい心をますます憂鬱にさせ、三階の病室にいく途中の足は、鉄にでもなったかのように重かった。
「理沙、良次君がきてくれたわよ」
ドアを開けて理沙の母が一声かけたとたんに、理沙の金切り声が飛んだ。
「ダメッ、入ってこないで。絶対会わないから」
「せっかくきてくれたものをそんな風に言うもんじゃありませんよ」
理沙はすっぽり毛布を被ったまま、顔を見せようとはしなかった。
「ごめんな、こんな目にあわせて」
「関係ないわ。お願いだからここへは二度とこないで!」
「いいかげんにしなさい。ほんとに嫌われてしまうわよ」
取り付く島がないとはこのことだった。母が毛布を引き離そうとするが、理沙は両手でしっかり毛布を押さえ、離そうとはしなかった。右腕には、押し倒されたときにでもついたのだろうか、痛々しい引っ掻き傷が残っていた。
「だからもう終わりだって言ってるでしょう。しつこくするんだったら、舌を噛み切って死んじゃうから」
理沙はヒステリックになってわめき散らした。
「もう、しょうがないわね。せっかくきてもらったのにごめんなさいね」
理沙の母は目配せして、良次に外に出るよう促した。
「またくるよ」
「だめ、今度は部屋の中には絶対入れない。もう、ほかの人を見つけて仲よくやって。さようなら」
本気でないことは、震えた涙声が物語っていた。なにが理沙をそこまで意固地にさせるのか、良次の中ではさっき思った最悪の連想がまた頭をかすめた。
「それとさ、大学受かったよ。合格通知がきたんだ」
「・・・・・」
理沙はなにも言わなかったが、身体の向きを変え良次に背を向けたのが、良次には喜んでくれたように見えた。
「理沙のわがままで、ほんとにごめんなさいね」
「明日もきます。いや、毎日きます」 そんなに気にするようなことでもないのに、無事にすんだことだけでも喜ばないといけないのにと思ったが、理沙にとってはそれではすまないのだろうな、とも思った。
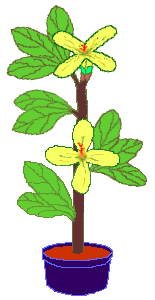
それからも理沙はがんとして、良次を受け入れようとはしなかった。退院してからは自宅に足を運んでも、一切良次に会おうとはしなかった。そればかりか学校にもプッツリいかなくなってしまい、登校拒否を続けていた。理沙の母の話しでは、昼間はまったく出歩かず、暗くなってから夜な夜なうろついて歩くということだった。「犯人が掴まったわけでもないのに」と母が叱ると、「敵討ちをしてやる」と言ってナイフを持ち歩いているということだった。理沙の母はほとほと困り果てた様子で、良次が電話をしたり自宅を訪れると、「ごめんなさい」をくり返すばかりだった。
卒業式を終えて、東京へ出る予定にしていた一週間前の晩のこと、突然、理沙から電話があった。
「ねえ、今すぐ逢いたいの。家の近くの公園でまってるから、すぐにきて」
「家の近くって、あそこ・・」
話しが終わらないうちに、電話は乱暴に切れた。良次はなんの迷いもなく家を出て、タクシーをつかまえると飛び乗った。
よりによってこんな時間に事件のあった公園にこいとは、理沙がなにを考えているのか検討もつかなかったが、とにかくいかないわけにはいかなかった。このまま理沙に会わないまま東京に出てしまったら、喉元に刺さったトゲのように、いつまでも心残りになることはわかりきっていた。
(ナイフで俺を刺そうというのか)
理沙が、自分を少なからず恨みに思っていると考えていた。理沙に刺されて死ぬ、それもいいさと思った。
タクシーを降りると、街灯が一つだけの薄暗い公園に理沙を探した。街灯とは反対側のベンチにぼんやりと黒い人影が浮かんだ。
「理沙、元気にしてたか? 理沙にツッパリなんて似合わないぞ」
なにも答えず、うずくまるようにしていた。スタジャンにジーパンの格好は、セーラー服の理沙とは様相を一変していた。「しばらくぶりなんだから顔を見せてくれないか」
両手で肩を抱き上げようとすると、理沙は叫んだ。
「やめて、恥ずかしいから見ないで。昔の私とは違うの」
そっと肩を包むように抱いた。
「理沙、なにがあったのか俺にはわからないけど、もう忘れよう。いつまでも相手の男を恨んでいたって苦しむのは結局自分だけで、なんの得にもならないぞ。そんなことを考える暇があるんだったら俺のほうを向いててくれよ」
理沙の身体が小刻みに震えており、なにかを必死でこらえているようだった。しばらくして理沙は、か細い声でつぶやくように言った。
「疲れちゃった、助けて。私を生き返らせて」
「うん。俺はどうすればいいんだ?」
「東京にいっしょに連れてってほしいの。ここにはいたくない」
「そうか。でもなあ」
「いや?」
「そうじゃない。生活のことを考えると、理沙を食わしてやれるかなあと思ってさ」
「それなら私も働くから大丈夫。それにね、怒らないで聞いてほしいんだけど、しばらくの間だったらお母さんが仕送りしてくれるって」
「えっ、お母さんも知ってるのか?」
「さっき相談したの。理沙がそれで立ち直れるんだったらいいわよって」
「ふーん、そうか。じゃ、いつまでも助けてもらうっていうのも抵抗あるから、少しのあいだぐらいだったらかまわないかな?」
「うん、ありがと。うふふ、よかった。だめだったらどうしようかと思ってた」
何ヶ月ぶりかで見る理沙の笑顔だった。ツッパリの格好はしていても、そこにはまちがいなく元の理沙がいた。
「ばかだなあ、だめだなんて言うわけないだろう。そうか、じゃ、東京にいったらいっしょに住むことになるんだなあ」
「良次くん、私キズものよ。それでも平気?」
「ばか、怒るぞ。もともとあんなことでグレてしまうほうがおかしいんだよ」
理沙は体を入れ替え、力いっぱいに抱きついてきた。理沙の全身からは溢れるほどの熱気が伝わってきた。まるでそれは、取り付いた悪魔を必死に追い払おうとしているかのようでもあり、異様な妖気さえ感じられた。だが時間が経つにつれ、それはしなやかなあたたかさに変わり、良次の五感をほんのりとさせた。
「どうだ、落ち着いたか?」
「うん」
「それで、お母さんとお父さんは結婚したのか?」
「いえ、私のことがあったからまだよ。だから、ガンは早くいなくなったほうがいいのよ」
「そんなことはないさ。それとさ、理沙に約束してほしいことがあるんだ」
「うん、なあに?」
「高校のことだけど、T学園は中退になってるわけだろう。東京にいったら別の学校にいって、高校だけは卒業してほしいんだ」
「うん、わかった。T学園からは卒業証書はもらえなかったわ。三学期は全然いってないものね。でも途中から入れる高校なんてあるの?」
「親戚の人でW大にいってる人がいてさ。その人から聞いたことがあるんだけど、全日制と通信制を採用してて、ほかの高校の中退者は、その学校でとった単位も有効になる高校が東京にあるんだってさ」
「ふーん、じゃそこを考えてみる。高校中退じゃ、将来子供に笑われちゃうものね」
そこまで言って、良次の顔を見つめ直してくる。「私ったら、いやだー」
理沙は勝手に想像して、勝手に照れた。暇があれば図書館にいって本を読んだり勉強したりする子が、学校へいくのが嫌いなわけはなかった。
「俺もな、ほんというと司法試験を受けてみるつもりなんだ」
「前はそんなこと言わなかったのに、やっぱりそうなんだ」
「はは、笑われるだけだからな。まあ、すぐには無理だから、大学在学中に司法書士の資格をとってさ。卒業したらそれでメシを食って、あとは三十ぐらいまでを目標に挑戦してみるつもりさ。だから、およそ贅沢なんてさせらんないぞ」
「うん、良次くんといっしょだったらどんなことでも平気よ。東京にいってからも、二人で図書館通いをしそうね」
「はは、そうだな」
理沙は急に、良次が気持ちいいのを通り越して痛いほどに、さらにギュッーと抱き締めてきた。
「良次くん、もう一つ聞いてほしいことがあるの」
「うん、なに?」
「ホテルっていったことある」
「な、なんだ。突然に?」
「今から私を連れてって。メチャメチャにしてほしいの。ここであったことを全部洗い流してきれいになりたいの」
その言葉を受け入れるには、まだマスターベーションの経験しかない良次には、かなりの勇気を必要としたが、理沙に恥をかかせるわけにはいかなかった。
「うん、わかった。いこう」
いつも通学する道筋の途中にラブホテルが一つあり、そこにいくつもりで国道に出た。ふと、青柳からコンドームの使い方を教えてもらってなかったことを後悔した。

|

|

|

|

|