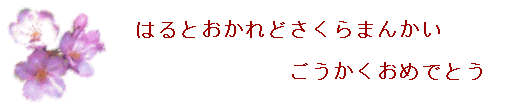
10章 胸ポケットの電報
東京のN大学での推薦入学の試験も無事終わり、それから三日後、朝から一通の電報を待っていた。そう、試験の合格通知である。合格、不合格にかかわらず、昼までには届くように発送するとの大学側の話しだったが、時計は既に午後一時を回っていた。
N大学への推薦入学は、工学部ではあるが毎年、二、三名の者が入っており、またこれまで学校推薦を受けて落ちた者は一人もいなかったので、まず合格はまちがいのないところだったが、それでも良次の場合は工業高校から法学部への進学ということで、大学側ではかなり面くらっているはずだった。それだけに合格通知を見るまでは気が気ではなかった。担任教師には、通知を待つため午前中は休みをとって午後からいくと話してあったが、これでは一日休まなければならないな、と思い始めた矢先のことだった。
「ごめんください」と言って、玄関の扉をコツコツ叩く者がいた。良次は飛び跳ねていって玄関の扉を開いた。
「滝田良次さん宛に電報です」
「はい」
受領証に判を押すのももどかしく、電報を読む。
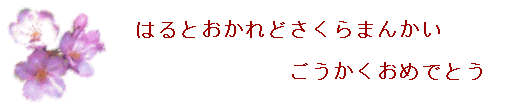
「やったあ!」
突然の大声に配達の電話局の職員は目を丸くして驚き、思わず後退りをしたがその意味はわかったとみえて、ニコッとしながら玄関の扉を閉めた。良次はうれしさのあまり興奮してしまって、胸がドッキンドッキンするのを抑えきれなくなり、しばしのあいだ、畳の上に大の字になって収まるのを待った。気分が落ち着くと電報を鞄にしまい学校へ急いだ。不思議とこういうときの時間の経
つのは遅く、通い慣れた道がよそよそしく思えた。
学校に着き自転車置き場から校舎に向かう途中、ばったり青柳と出くわした。一見して気落ちした様子の母がいっしょだった。
「まだこんな時間なのにどうしたんだ?」
「ちょっとな。こいつと話しがあるから先にいっててくれよ」
青柳が母にそう言うと、母は良次に軽く会釈をして校門に向かって歩いていった。
「どうなってんだよ?」
「ふっ、クビさ、クビ・・。退学届けを叩きつけてやったよ」
青柳は照れ隠しにニヤッとしながらふてくされた態度で言った。
「そうか、だめだったか」
青柳はこの一週間、謹慎処分となって学校を休んでいた。停学ならその処分だけですむ可能性があったが、謹慎となるとそのまま退学になるかもしれない、というのがもっぱらの噂だった。
「科長が、なにも高校で人生が決まるわけじゃないとかなんとか言ってたけどな。だったらうるさいこと言うなってんだよ」
「で、結局彼女はどうしたんだよ?」
「あいつも退学だよ。似た者どうしってことだな」
「違うよ。こっちだよ、こっち・・」
良次は人差指で自分の腹を差した。
「ああ、堕ろさしたよ。しぶしぶな。子供に罪はないからな。責任を負えないものを産ますわけにはいかないさ。遊びは遊びできれいにやらないとな。それをできてしまったら産みたいだからな。女の言うことなんてあてにならないよ」
青柳はもっともらしい言い分を捲し立てた。
「ふーん。でも、おまえなら妊娠しない方法は知ってるわけだろう。なんできちんとしなかっただよ」
「それがアレをつけるとおもしろくないんだなあ。ナマでやるのが一番さ」
「ふっ」
青柳らしいことではあったが、そのことが青柳の人生をも狂わしかねないことを考えれば、やはり馬鹿げていると思った。
「おまえのほうはどうなんだよ、例のセーラー服の彼女さ」
「ああ、相変わらずさ。おまえのようなわけにはいかないからな。図書館とか公園が関の山さ」
「それが一番だよ。やりたいことやってこの様じゃ、しょうがないさ」
「これからどうするつもりなんだ?」
「大検でも受けようかとも思ってんだけど、もう勉強する気力も起きてこないしな。しばらくはバイトでもやってゆっくり考えるさ」
いかにも投げ遺りな感じで青柳は言った。
「そうか、まだ三月まではいるからさ。遊びにこいよ」
「ああ、ところでおまえこそ今頃登校か?」
「う、うん。ちょ、ちょっとお袋が熱出したもんだからさ」
思わず胸ポケットに入れた電報を押さえ込む。
「ふーん。じゃ、彼女によろしくな」
校門を出ていく青柳の後ろ姿は、さすがに寂しさが隠せなかった。

職員室にいくと、担任の井上が空き時間とみえて本を読んでおり、良次が入っていくと待ち兼ねていたとばかりに、他にも残っていた教師といっしょに良次のほうを注目した。青柳のことが頭に残り暗い表情をしていたせいで、井上は落ちたとでも思ったのだろうか、すぐに笑顔を消して目を伏せた。だが電報を鞄から取り出すと、またもとの女性教師らしい明るい笑顔をつくった。
「おめでとう。よかったわね」
照れてなにも言えなかったが、職員室のあちこちから「おめでとう」の声が飛びかった。
就職組の連中は全員が就職先が決まってしまい、気が緩んで教室の中はいつもざわついた雰囲気になってしまっていた。ともすれば進学組の連中までが、その雰囲気に呑まれてしまい、勉強が手につかなく者もいる有様だった。良次も多少は引き込まれたようで、最近は早く受かって受験勉強から解放されたいと思うようになっていた。
井上が気を利かし、
「六時限目もそろそろ終わるころだから、もうきょうの授業は出なくてもいいわよ」と言うので、その言葉に甘え学校を出て図書館に向かった。まだ理沙がくる時間でないのはわかっていたが、待ち受けて少しでも早く教えたかった。
勉強の必要もなくなったが、一応参考書を机に広げ、ただ無意味な時間をぼっーと過ごして理沙がくるのを待った。顔は机をむきながら目は常に入り口カンウターを向いていた。三十分、一時間と待ったが理沙は現れなかった。

|

|

|

|

|