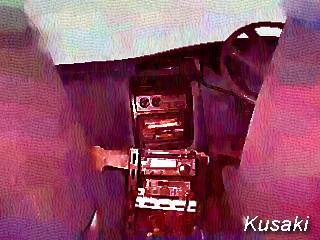
4 ダイイングメッセージ その2
現場は川崎街道から外れ、JR南武線と多摩川にはさまれた住宅街の路上だった。廻りにはところどころ畑が目につくものの、一軒家やアパートが建っている。むしろ朝方まで発見されなかったというのが意外に思えた。パトカーを筆頭に警察の関係車両が警光灯をチカチカ点滅させ警官や鑑識課員が、そして警察犬までが忙しなく立ち回っている。まだ朝が早い時間なのにロープで仕切られた外側には、野次馬までが声をひそめてワイワイガヤガヤやっていた。
「いちいち説明するのもめんどくさいからさ。俺のあとに黙ってついてきて」
関口が軽く敬礼をすると、ロープの前に見張り番をしていた警官がなにも言わず、さっと敬礼を返して張り巡らせているロープを上げてくれる。萩野もそれらしい顔をして関口のあとについていった。
「おはようっす。こちらは例のアマチュア無線電波を受信した友人です」
関口は所轄署のリーダー格らしき刑事に、萩野を紹介した。
「ああ、どうも。凶器はまだ見つかってないのですが鋭利な刃物で胸をひと突きですよ。少しだけ抵抗したような跡はあるんですが、比較的きれいに運転席に収まっているところを見ると、犯人はまったくの見ず知らずというわけではなさそうですね。ただ被害者の財布や免許証はもとより、自賠責保険や車検証なんかの書類のたぐいがすべて失くなっているんです。しかも、車のキーも抜いてあるんですよ。単純な物取りのしわざとは思えませんね」
「ふーむ。だまされた、と言ったのにまちがいはないね?」
関口は刑事に向いていた顔を、ふいに萩野を振り返り訊いてきた。萩野がうなづくとまた刑事を向いて言う。「昨日の交信相手ということであれば顔見知りの犯行と思っていいでしょうから、なにかの証拠を隠すためかもしれませんね。被害者の身元はわかっているんですか?」
「いま、車のナンバーから調べさせているところです。ちょうど遺体を搬出するところですから、その前に見てやってください」
話しながら事件のあった車に近づいていく二人とは、遅れぎみになった萩野が後ろから声をかける。
「関口さん、俺はここで待ってますから」
「いや、ハギさんにも被害者の顔を見てほしいんだ。身元を確認するためにさ。同じハムなんだから知ってる人かもしれないだろう」
「はあ」
関口から誘われるままに半ば刑事気取りでここまでやってきた萩野だったが、このときになってはじめて後悔した。
「大丈夫だよ。みんながいるんだから、はは」
萩野は重い足取りで、関口から腕をとられるようにして一歩一歩車に近づいていった。
「朝方まで発見されなかったのは、スモークガラスと被害者がリクライニングシートを全部倒して寝てる格好をしてたせいでしょうね」
刑事がドアのガラスを指差して言った。両サイドとリヤのウィンドにはスモークフィルムが処理されており、完全に明るくなったいまでも顔をガラスにすり合わせるようにして覗かないと、中はほとんど見えなかった。
「さ、ハギさん。しっかり見てくれないと困るよ」
関口が意地の悪いニヤつきを浮かべて身体全体に毛布がかけられた被害者の、頭の部分だけの毛布を捲った。
「うっ!」
萩野は腰が引けながらも、苦痛に引き攣った被害者の顔を拝んだ。
そう、拝んだというのがぴったりだった。関口が毛布をもどしたあと、つい両手を合わせてしまったのだ。佐々木の死に顔の無我の境地にでも入ったかのような穏やかな表情とは似ても似つかぬ、恨み辛みを満面にこめた顔つきだった。
関口が背中をさすりながら訊いてくる。
「大丈夫かい。どう、知ってる人かい?」
「いや」
萩野は力なく首を横に振った。
ふっと、何気なくもう一度毛布に包まれた被害者の方に視線をやったとき、助手席のトランシーバーが目に止まった。
「あれ、電源スイッチが切れてませんか?」
プッシュ式のスイッチだけに見ただけではよくわからない。関口も運転席の中に顔を突っこむようにして言う。
「うーん、もどってるようだけど、それがどうかしたかい?」
「だって、俺が聞いた相手だとしたらおかしいじゃないですか。あのようすではしゃべったあとそのまま事切れたと思うんですが、そのあと自分で電源スイッチを切ることができますか?」
関口は思わず刑事と顔を見合わしたあと、刑事に尋ねる。
「鑑識の方がスイッチをもどしたということはありますか?」
「いえ、鑑識作業は全部終えたわけではないですから機器類は一切動かしてません」
「それじゃ、試しにスイッチを入れてみてもいいですか?」
刑事は廻りにいた鑑識課員に都合を訊いてから、
「いいでしょう。やってみてください」
と言った。三人は助手席側に廻り、代表して関口が膝をついて押す役になる。白い手袋をはめて言う。
「いいですか、押しますよ」
「カチッ」とプッシュボタンは奥に入りこんだが、ランプや液晶表示に明かりが灯ることはなかった。
「ああ、キーが入ってないからですよ」
萩野がそう言うと、二人も思い出したように苦笑した。が、関口がすぐ真顔になって納得したようすで言う。
「でもこれで、電源スイッチが切られていたことだけは確認できましたね。マイクはどのへんにあったんでしょうか?」
運転席の側からじっと見守っていた鑑識課員が言う。
「被害者の左側の太股をコードが跨ぐようになって、マイクは床に垂れ下がっていました。指紋が検出できてますので、署に帰ってから被害者のものかどうか照らし合わせてみるつもりです」
「ふむ、被害者のものと一致すれば死ぬ間際まで電波を出していたとみていいな。それと、メモリーに残されている周波数を確かめたいのですが、別の車に移して電源につないでみてもかまいませんか?」
関口は所轄の刑事ではないだけに、いちいちお伺いを立てる。向い側の鑑識官が刑事から訊かれる前に目でうなづいた。
「どうぞ。でも、このアマチュア無線の機械は周波数が430メガ帯しか出ないトランシーバーなんでしょう。確認するまでもないように思いますが」
「ええ、念のためですよ」
まず、トランシーバーからアンテナコネクターと電源コードのソケットを外し、本体もモービルブラケットから取り外す。それを萩野の車までもっていき、助手席において電源だけをつないだ。
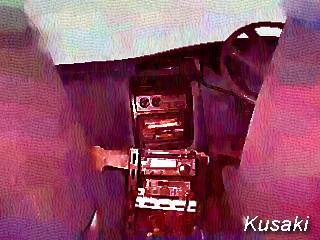
「さてと、入れますよ」
みんなが息を飲む中、関口はおもむろに電源スイッチを押した。すると全体にオレンジ色のイルミネーションが灯り、その中にグレー色の432.30の数字が浮びあがった。
「まちがいないですね。昨日、僕がQSOをやってた周波数ですよ」
「なるほど、そういうことでしたか」
刑事が二度、三度と首を縦に振った。関口がログを刑事に見せながら言う。
「この局と交信した時間の一、二分前に助けを呼ぶ電波を受信したそうですから、死亡推定時刻がこの時間と同じ時間帯にくるようであれば、ハギさんが聞いた声の主とあの被害者とは同一人物であると断定していいでしょう」
「ふむ、そういうことになりますね」
「それにしても被害者が、だまされたと言ったからには犯人は知り合いの可能性が高いわけですからね。そのとき名前まで言ってくれればねえ。すぐにでも解決するかもしれないんだが」
関口が萩野を見やると、周囲の者の視線も萩野に集中した。
「いえいえ、聞いてませんよ」
むきになって首を振ったおかげで、それでなくとも櫛すら入れてこなかった髪が益々ざんばら頭になった。
「しかし電源スイッチが切られていたというのは、どういう風に説明したらいいんでしょうね?」
と、刑事が訊く。
「おそらく犯人は刺したあと、一度は逃げたと思うんです。そのあと冷静になって、自分と結びつけられてしまうような資料を残しておいたのではいけないということで、書類関係の一切を手当たり次第に持っていったのでしょう。そのときトランシーバーに電気が入っていたのを見てスイッチを切った、車のキーも抜いていったということじゃないでしょうか。被害者のリクライニングシートが倒れていたのも、発見を遅らすために犯人がやっていったのかもしれませんね」
関口の話しの頃合を見計らって、若い刑事がリーダー格の刑事に一枚のメモ用紙を渡して報告した。
「車の持ち主の住所がわかりました。隣りの多摩市のアパートですね。持ち主とガイシャが同じなのかどうか、ポラロイド写真を持ってあたってこようと思います」
「ああ、すぐにいってくれ」
刑事は関口に向き直って言う。「いまのところ目撃者は現れてませんでね。せめて住まいの方からでもなにかわかるといいのですが」
「ええ」
関口はあっさり答えた。刑事が離れていったあと萩野が小声で訊く。
「アパートの方はあまりあてにしてないようですね?」
「いや、そんなことはないけど。たぶん、車のキーにはアパートの鍵もついていたろうから、犯人は部屋も家捜しして証拠になるような資料はきれいに始末してると思うね。時間はまるひと晩あったわけだから充分だろうしね。そうじゃないと、キーを抜いていった説明がつかないんだ。犯人はかなり用意周到に行動したか、まったくの臆病者のどちらかだよ。というのは、殺した以上止どめを刺すのが普通だろう。それをしてないということは、被害者と無用の取っ組み合いになるのを避けて死ぬのを離れた場所で待っていたか、そうでなければ怖くて一目散に逃げ出してしまったということだね。いずれにしろ車にもどってきて、被害者が電波を出した形跡には慌てたんじゃないかな。おそらく車からもアパートからも犯人の指紋が検出されることはないと思うよ」
遺体は担架に乗せられて、警察のワゴン車に運ばれていった。そのあとも運転席周辺を中心に指紋の検出作業は続いた。
その作業を関口といっしょに数メーターの距離から見守っていると、鑑識課員が運転席の写真を撮るのにストロボをたいた。そのとき、ストロボの光がドアの内側のビニールレザーに反射し、そこに書かれた文字らしきものが萩野の目に残像となって残った。
「すみません、ちょっと見せてもらっていいですか」
「かまいませんけど、触らないでくださいね」
萩野はビニールレザーに目を凝らすようにして見入った。黒のビニールレザーの上に黒のボールペンで書いてあり、しかも擦れてしまって消えかかっているのでよくよく見ないとわからないが、アルファベットの文字が読み取れるのだ。
「これはなんですかね?」
「さあ、いたずら書きでしょう」
鑑識課員はとうに気がついていたらしく、こともなげに答えた。
「どうかしたかい?」
関口も何事かと首を寄せてくる。
「これ、Jに見えませんか。そのあとはH、いやAかな。続いて1。そしてU、Iかな。JH1UI?」
「うん、下にも書いてあるなあ。1NI・・・・。なんだあ、ICの型番かな。あん? 待てよ、上の方はJA1UT・・じゃないのかい」
「となると、佐々木さんのコールサインかもしれませんね。どうしてこんなところに?」
「うーむ、なにか引っかかるなあ。チョウさん」
リーダー格の刑事を関口はそう呼んだ。
「なにか手掛かりが掴めましたか?」
「まだわかりませんが、ちょっと気になるものですからね。このいたずら書きのようなものを赤外線カメラで撮れば、見えない部分もボールペンでなぞられて凹んだ跡が写真に浮かんでくるのではないですか」
「ふむ、やってみましょう。ただ、ここには持ってきてませんから車を署に運んでからにしましょう」
ほかにもなにかないか、二人は鑑識の連中に煙たがられながらも車の内から外まで、顔を車体に擦りつけるようにして見て廻った。

|

|

|

|

|