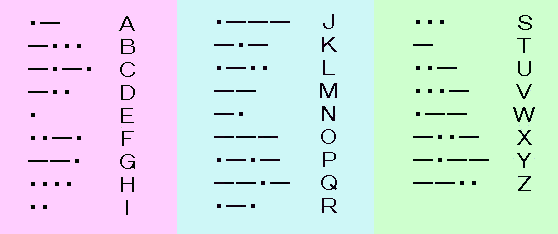
AREA5 呼出符号の皮肉
その3
翌日からは業務日誌を毎日一ページづつ埋めていくことになった。ともすれば外に出るのを忘れてしまうほど、マイクにかじりついていた。HF、VHF、UHFを問わず、CQを出している局を見つけては声をかけた。単純に局数をかせぐのならCQを出せばいいのだが、最初のQSOがきいて自分からはなかなか出せないでしまっていた。144MHzと430MHzはチャンネルが混み合っていることが多く、運用するのは自然と7MHzと50MHzが多くなった。
二週間ほどたった日、亜香里が3級を取るように勧めてきた。
「3アマなら出力が25Wまで出せるし、電信もやってみると案外おもしろいものよ。筆記試験なら4アマとあまりかわらないし、モールス符号は一ヶ月もあれば覚えられるわ」
確かに7MHzではQRVしている局数が多いため、CQを出している局を見つけ呼びかけてみても、必ずといっていいほどほかにも呼ぶ局がいるので一発でとってもらえるのはめったにない。二度、三度と呼んでやっととってもらえるような始末だった。25Wになれば当然電波は強くなるわけだし、それだけよけいな手間をとらなくてQSOできそうな気がした。
「せっかく勉強したんだから、忘れないうちに3アマも取ってしまった方が賢いやり方ってものよ」
と亜香里がダメを押す。4月から大学に通うようになれば、そうそうアマチュア無線ばかりというわけにはいかない。三月までがいいチャンスなのかもしれない、と思えば答えは一つだった。
昼下がりの午後、亜香里が父親のエレクトロニクスキーヤーとヘッドホンを持ってやってきた。プラグをトランシーバーの背面に差し込むと、それで用意は終わりだ。さっそくキーを左右に振ってみる。
「だめよ。正和さんは受信ができるようになるまでは、一切キーに触っちゃだめ。送信を先に覚えてしまうと受信がなかなかできなくなってしまうの。受信を先に覚える分には、送信は簡単に打てるようになるわ。実技試験が受信だけで送信がないのは、そういう理由があるからなのよ」
亜香里はそう言うと、意地悪くキーを自分の手元に引き寄せた。
「じゃあ、はじめましょう。さ、ヘッドホンを付けて」
「いいよ。そんなもの必要ないよ」
「始めのうちは付けた方がいいのよ。スピーカーだけでは音の微妙な違いがわかりにくいの。ある程度覚えたら付けなくてもいいわ」
「わずらわしいなあ。耳だって痛くなるし・・」
ぶーぶー言いながらもヘッドホンを頭に回す。
「あ、それは見ないでいいの。わたしが代わりに紙に書いていくわ」
めでたくJARLの会員となり、そのJARLから送られてきた会員手帳を亜香里は取り上げると机の引出しの中へ放り込んだ。
「どうして? せっかくモールス符号表が載ってるんだから、これを見て覚えたらいいんじゃないの」
「そりゃ悪くはないけど、アルファベット順に覚えていくよりも、同じような符号を並べて覚えた方がその違いを早く聞き分けられるようになるの。たとえばQがツーツートツーだけど、Yがツートツーツーでしょう。これが意外といっしょくたんになってしまって、いつまでもまちがえてしまうものなのよ。ほかにもFとL、短点が続いたのではHとSも区別がつきにくいわねえ。それに試験のときには順序よく出てくるわけじゃないでしょう。最初はやりづらい面があるけど、一つ一つ覚えていけば最後にはABCって順に出てくるようになるわ。こっちの方が絶対近道よ。ま、わたしに任しといて」
と言って起伏にかけた胸を叩き、おどけてみせた。
『・・・− ・・・− ・・・−』
「どうお、きれいに聞こえてるでしょう」
「これ、お空に出てるのかい?」
「いいえ、パワーメーターが振れてないでしょう。モニターしてるだけよ。それじゃいくわね」
『・ ・・ ・・・ ・・・・』
「いまのはE、I、S、Hね。ト・E、トト・I、トトト・S、トトトト・Hね。いーい。覚える順序はE・トじゃなくて、あくまでト・Eよ。これを逆に覚えてしまうと、ストレートに文字が浮かんでこないのね。同じことを何度も打つから、正和さんは一つ一つ書き取っていって」
言われるままに落書用のノートを開く。ボールペンを持って向かい、亜香里が打つモールス符号を根気よくノートに書き取っていく。何回かくり返しているうちにHと書いた後、スピーカーからはEの符号ではなくまたHの符号が流れた。Eは短点一つだからいやでもわかるが、やはり亜香里がはじめに言ったとおりSとHの区別がつきにくく、いつのまにかごっちゃになってしまっているのだった。
「じゃあ、今度はSとHだけを打つわ」
『・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・』
二つのモールス符号をくり返し打たれれば、理屈ではなくリズムでその違いがよくわかる。書き取りをやること十分、除々に二つを聞き分けられるようになった。
「次は四つの符号をばらばらに打つわね」
さすがに入り混じって打たれたのでは、はじめのうちはまごついたが、二十分もしたころにはほとんどまちがいなしに取れるようになった。
「もうだいたいとれるようになったから、別のをやろう」
「そうね。今度は長点符号にいくわ。T、M、Oの順ね。一日に七つやれば、四日で全部を暗記できる計算になるでしょう」
『− −− −−− − −− −−− − −− −−−』
短点符号に比べれば、時間が長くかかるだけに点と点の区切りがしっかり頭に残る。順不動に打たれたのも含めて、二十分で合格点に達した。
「それじゃ七つまとめて打つわね。今度はいままでのようなわけには!?」
亜香里が突然ギョッとした顔で庭を見やった。正和もその方向に視線を向けると、千華が微笑みながら立っていた。
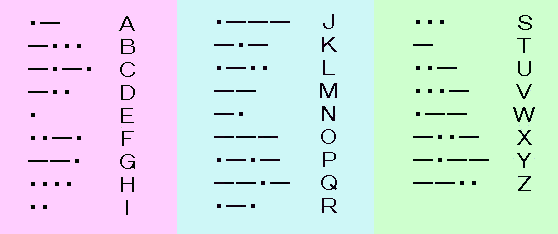
「ごめんなさい。何度呼んでも返事がなかったものだから」
「ああ、ヘッドホンを付けてモールス符号の練習をしてたもんだからさ。今度は3級を取ろうかと思ってるんだ。とにかく上がんなよ」
「そう、すごいわね。お邪魔しちゃったようでほんとにごめんなさい」
千華は亜香里に軽く会釈しながら言った。そして正和の目をじっーと見つめると、もう一言付け加えた。「そうだったの」
正和がどぎまぎしながら言う。
「か、考え過ぎだよ」
亜香里もほんのり顔を赤らめ立ち上がった。
「わたし、そろそろ学校へいかなくちゃいけないから失礼します」
エレクトロニクスキーヤーを抱えて出ていこうとするのを、正和が引き止めて二人を互いに紹介する。
「こちら金野千華さん。大学のときの同級生なんだ。こちら川村亜香里さん。隣りの人なんだけどハムの先生でさ。全部彼女に教えてもらったんだ。実はこの前のKプラザホテルがわかったのも、彼女が調べてくれたんだよ」
「まあ、そうだったんですか。その節はよけいなご面倒をおかけしまして、ありがとうございました」
「いいえ」
はにかみながら出ていこうとする亜香里を、今度は千華がさえぎって言う。
「わたしはただの元同級生ですから、よけいなお気遣いはなさらないでください。それにお話ししたいこともあるんです」
最初は亜香里を見て言ったが、途中からは正和の方に視線をやって訴えかけるようにして話すのだった。
「まあ、まだいいじゃないか」
再度の説得に亜香里は再び腰を下ろした。
「これを見て」
そう言って千華が机の上に置いたのは従事者免許証だった。
「おお、きたのか。じゃあ、局免許を。あれ、なんだこれは?」
名前の欄には“金千華”と印字してあり、さらにその横に手書きで“金野千華”と記されてあるのだ。
「そのきちんと印刷されてあるのが、わたしの本名なの。手書きのは通称名なのよ」
「はあん?」
三人のあいだに一種奇妙な空気が流れ、しばし沈黙のときが続いた。
千華が「ふっー」と吐息をつくと、重い口を開いた。
「いままで黙ってたんだけど、わたし国籍は朝鮮籍なの。びっくりした?」
千華は正和の顔を上目遣いに、探るように見つめる。
「そうじゃないっていえば嘘になるかな」
「ずっーと言おう言おうって思ってたんだけど、どうしても口に出せなかったの。バレたらこれまでみたいな友だち付き合いはできなくなるんじゃないかと思って。お父さんの店にもみんなを連れていったことがなかったでしょう。お母さんは日本人だけど、お父さんは向こうの人なの。お父さんの話し方を聞けばすぐわかってしまうものね」
「そうだったのか」
千華の父親は大きな中華料理店をやっているということだが、友人が誰かれなしに、「一度招待しろよな。腹いっぱい食わしてくれよ」などと冗談半分に千華に催促したが、決まって千華は怒ったともとれるような表情で、「お坊っちゃまに合うような店じゃないの」とはぐらかしていた。
「昨日免許がきてからさっそく二人の申請書を、直接アマチュア無線振興協会の事務局に出しにいったの。そのときに聞いたんだけど、外国籍の人にはプリフィックスが”7J1”のコールが割り当てられるんだって。それだったら隠してても、いずれコールサインでわかってしまうものね」
「ふーん、そうなのかい?」
と、亜香里に訊く。
「ええ、以前は相互運用協定を結んだ国の人以外は、個人コールはとれなくてクラブ局での運用しかできなかったんです。それが政令が改正されて、日本の従事者免許をもっていれば国籍に関係なく個人コールがとれるようになりましたから、ずっと前進はしたんですけどね。特に朝鮮・韓国人の方には、国籍を知られたくない人は多勢いるんでしょうから、そのへんのところはまだまだ考慮する余地があるんでしょうね。いっそのこと、相互運用協定による局免だけを”7J”にして、日本の従免によるコールは国籍に関係なく日本人と同じプリフィックスを割り振っていけばいいと思うんですけどね」
「よくわかりませんけど郵政省の偉い人が決めることのようですから、わたしたちのレベルではどうしようもないですね。いずれにしても、大輔にも正和にも知ってもらういい機会だったから」
ひと呼吸おいてから、正和を探るように訊く。「これからもお友だちでいてくれる?」
「当たり前だよ。国籍がどこだって千華にはかわりないだろう」
「よかった。正和ならそう言ってくれると思ってた。最近はあまり露骨に嫌がらせをされることはなくなったけど、小さいときはなにかといじめられてね。中学になって家を引っ越してからは一切言わないようにしてきたの」
千華はいくぶん鼻声になって自嘲ぎみに言った。
「ふーん、おれたちにはわからないけど、いろいろあるんだろうな」
そんな言葉でしか慰めようがなかった。
亜香里が時計を気にしながら言う。
「それじゃわたし、そろそろいかないと遅刻しちゃから」
亜香里が立ち上がって後ろになったところを、千華が静かに、それでいて澄み渡るような声で呼び止めた。
「亜香里さん」
千華がかっと見開いた目で亜香里を食い入るように見る。そして深々と頭を下げて言った。「正和のこと、よろしくお願いします」
とうの亜香里は、最初は何事かといった顔で正和と見合っていたが、突然を顔を真っ赤にすると駆けるようにして出ていった。
「純情な子をからかうもんじゃないよ。夜の巷で鍛え上げたオネエサンとはわけが違うんだから」
千華はそれには応えず、亜香里のいなくなった跡に視線を向けたまま、ただ笑みを浮かべるばかりだった。

|

|

|

|

|