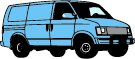
3 覗く牙 その二
「そうでしたか。それでは生活のほうは障害者年金か、生活保護でやってらしたわけでしょうね?」
「ええ、まあ!?」
「なるほど。それでしたら今こそ社会に対して恩返しをするときではないですか」
どこかで聞いたようなセリフだ。
「・・・・・・」
「お兄さんもそういうことがあったからこそ、ドナー登録をなさっていたのではないですか。せめて死んでからでもお役にたちたいと願っていたのではないですか」
「まあ、そんなことを言ってましたけど」
「菊池さん、臓器は一分一秒でも早いほうがいいんですよ。時間の経過とともに傷みが増していって、それだけ移植の成功率も下がってしまうんです。すぐにでもやらしていただけませんか」
教授は再度、承諾書を良次の前に突き出した。
「なにも兄は臓器を提供するために交通事故に遇ったわけじゃありませんよ」
さすがにそこまで言われると我慢がならなかった。「それに確か、臓器提供者保護法には遺族に対する説得の通算時間は二十分以内と定められているのではなかったですか?」
もともとそれほど興味もない問題だったので新聞記事の細かいところまでは読んでいなかったが、比較的大きな見出しでそんなことが書いてあったように記憶していた。
「いえ、三十分です。それにまだそんなに時間はたっていません」
「それじゃ記録を見せてください。あとから検証できるようにと、すべて記録に残すようにとの規定もあったでしょう」
これもつたない記憶からの、あてずっぽうだった。すると、教授が両手を押し広げて言う。
「まあまあ、菊池さん。私の言い方が癇に障ったんなら謝りますから、どうぞ気を静められてください。私は胸部外科の医者ですからね。受け持ちの患者の中には先天性の心臓病をわずらって苦しんでいる人が数十人います。その中の数人は心臓を別の健康な心臓に交換しない限り、いつ死んでもおかしくないという切羽詰った状態にあるんです。医者とすればそのうちの一人でもどうにか助けてあげたいわけですよ。ましてやお兄さんは、こういったときのために心臓を使ってくださいよ、ということでドナー登録をされたんじゃないですかね。それに応えてあげてこそ成仏できるというものではないでしょうか」
今度は攻め方を変えてきた。こう正面からこられたのでは、言い返す言葉がない。
「とにかく時間をください。二、三週間もつということであれば、そんなに慌てることでもないでしょう。それじゃ義姉についてますから」
教授は苦笑を浮かべるだけでそれ以上引き留めることはなかった。廊下に出ると長いすにすわっていた男が立ち上がり、良次に近づいてくる。
「菊池秀一さんの弟さんでらっしゃいますか? 私、こういう者ですが」
差し出された名刺を見ると“S火災海上保険株式会社”とある。
「加害者の方が加入されている損害保険会社の者です。奥さんがまだ落ち着かない状態にあるようですので弟さんにお話しをと思いまして。この度は取り返しのつかないことになってしまいまして、なんと申し上げてよいのやら」
「あ、そうか」
すっかり加害者の存在を忘れてしまっていた。「ええと、ぶつけた方はどちらにいるんですか?」
唾を吐きかけるとまではいかないまでもなにかしらは言ってやりたい。周りをきょろきょろ見渡すが、それらしい人物はいなかった。
「それが、申し訳ないんですが、きょうのところはこれないということなんです」
「人を轢き殺しておきながらこれないとはどういうことですか?」
つい、廊下に響き渡る大声で怒鳴ってしまった。
男はハンカチで汗を拭いながら言う。
「なんといいますか、加害者の方も被害者意識を持ってらっしゃいまして」
「事故を起こしたのはそっちでしょう。なにを言ってるんですか?」
「それが、事故はお兄さんが自殺行為とでもいえるような格好で、突然歩道から車の前に飛び出してきて起きたというんです。詳しいことは警察が捜査中ですのでどちらに原因があるかはまだはっきりしないのですが、とにかくそういうことがありまして」
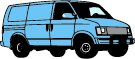
それを聞いて良次は愕然とした。兄は過去に二度、自殺未遂の経験があったのだ。だがそれは結婚前のことだ。可能性としては否定できないが、義姉といっしょになってからは考えにくいことだった。
「三日前に登録して飛びこみか」
「は、なにか?」
「いや、こっちのことです。仮りにそうだとしてもですよ。その方が轢き殺したという事実にはまちがいないんですから、謝罪があって然るべきじゃないですか」
「ええ、お葬式には必ず伺わせるようにしますので。ほんとに申し訳ありません」
加害者が加入している保険会社の社員とはいえ、第三者から頭を下げられたところでしょうがない。
相手にせずに立ち去ろうとすると、男はまた呼び止めた。
「あの、こんなときになんなんですが」
「まだなにか?」
「賠償の問題なんですが、対人の任意保険は最高で一億円のものに加入しております。ですから、それなりの保障はできるかと思います。病院への支払いはこちらから直接しますので、その点の心配は一切ありませんので。それからこれはとりあえずのお見舞ということで、どうぞお受け取りください」
男はうやうやしく茶封筒を差し出した。
「ああ、それはどうも。ここ数日は立てこんでいるでしょうから、いずれ落ち着いたときに」
最高額が一億でも、四十を過ぎた働ける見込みもない精神病の男となればその半分も出ないだろう。それどころか、強制保険額の三千万でも充分まにあうようにも思われる。それでも義姉にとっては、あとあと楽に暮らしていけるだけの金額のものは下りるだろうことが唯一の救いといえた。
ICU室に戻ると義姉が兄の腕を擦り、目を見てなにかを話しかけるようにしている。赤身を帯びた兄の顔はそうしていることになんの不自然さも感じさせない。とても死顔には見えないのだ。試しに良次も足の脛に触ってみる。あたたかい。どこが死体だというのだろうか。脳死の理屈をしっかりわかっていない限り、とても納得できるものではない。
「義姉さん、薬は飲んだ?」
「・・・・・・」
義姉は無言のまま首を横にふる。
「それじゃ、薬を飲んで少し休もう」
脇で見守っていた、ナースハットに三本線が入った年配の看護婦が言う。
「突き当たり右側の部屋をとってございます。お食事も用意してございますので、どうぞ召し上がってください。このままでは奥さんまで参ってしまいます」
「それはどうも。義姉さん、いこう」
グズるのではと心配したが、義姉は良次の誘うままに立ち上がった。
部屋は差額ベッド料をかなり取られるような個室らしく、ホテル並のベッドに応接セットが備えてあった。ソファにも毛布が用意してあり、テーブルには店屋物の食事が二人前並べてあった。
「せっかくだから食べようか」
義姉はまた一言も発しないまま首だけを横にふる。まるで、言葉を忘れてしまったかのようだ。
「そう。じゃあ、ベッドによこになるといいよ。俺はソファで休むから」
それには返事をせず、義姉はトイレに立った。
良次とて食事が喉を通るような心境ではない。ソファにゴロンとなって、たばこに火をつけた。吹いた煙が口許から乱れる。息を強くして、フッーと遠くまで飛ばそうとしてもジェット雲のような直線にはならなかった。
義姉はトイレから戻ると、良次に背を向けてベッドにもぐった。

|

|

|

|

|