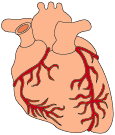
3 覗く牙 その三
一夜明けた翌日、午前中は家と会社に寄り、午後になって病院に戻った。
義姉は相変わらず兄に身を寄り添うようにしていた。その献身的な姿を見ていると、なんとかしてやりたい気持ちになってくる。昔見たサイボーグ人間をテーマにしたマンガの中で、頭にやたら線をつけたサイボーグが電気を入れたとたん、むっくり起き上がって歩き出すシーンがあった。現代医学なら兄だってそうなふうにならないか、と思いたくなってくる。
「すみません、ちょっとこちらに」
看護婦がカーテンをちょっとだけめくって、廊下に誘い出す。
「先生が、教授室のほうにお越しいただくようにとのことなんです」
きたな、と身構えて教授室へむかう。
「やあ、どうも。どうです、説得していただけましたかな?」
教授が待ちかねたようすで言う。
「ええ、それなんですけどね。今の義姉には無理ですねえ。抗精神薬のせいでかなり眠いはずなんですけど昨日の夜、ちょっとよこになっただけで、ずっーと付き添ってますからねえ」
「ふむ、そのようですね。この際どうでしょうか、菊池さんから書類にサインをいただくということで」
「いやあ、そんなことはできません。それに僕がサインしたからといって義姉は兄から離れませんよ」
「それは治療のための手術をすると言えばどうにでもなるでしょう」
「そんな期待を持たせるような嘘をつくわけにはいきません」
はっきり断ればいいのだが世話になったいるのは確かだし、義姉が精神科の細野教授にこれからもめんどうみてもらうことを考えれば、あまり露骨な言い方はできなかった。
教授は渋い顔を窓のほうに向け、腕組みをしてじっーと考えこんでしまった。しばらくしてから、また良次のほうを向いて話しを始める。
「臓器提供者保護法ができて移植治療にゴーサインが出てからは、一日千秋の思いで待ってらっしゃる患者さん多勢いるんですよ。きょう、明日、命の灯し火が消えかかっているような人がこの病院だけでも何人かいるんです。助けてやってくれませんか。助かる命を見捨てることはないじゃないですか」
最後には隣りの部屋まで通るような声で言った。
そんなことを言うなら先に兄の命を助けてみろ、と言いたくなってくる。今度は良次が口を八文字に結んでいると、教授の表情が急にほころんだ。
「わかりました。それじゃ、こうしましょう。承諾書にサインをしてもらえましたら、その敬謙なお気持ちに対し、またお兄さんの霊を慰めるためにも私どもから慰霊金をお送りしましょう」
一瞬、なにを言ってるのかと思う。病院から治療費を請求されることはあってもお金をあげましょうなどと、冗談にも聞いたことがない。が、ピーンと閃くものがあった。
「えっ、それじゃ臓器売買・・・」
驚きのあまり立ち上がった良次を制するように、教授も仁王立ちになって言った。
「菊池さん! 誤解してもらっては困りますよ。私は心臓を提供していただいた結果、感謝の気持ちとしてお出ししようといってるんです。これだけ出しましょう」
教授はそう言って、指を二本立てた。
二千万。ここしばらく頭から離れない借金の額とピッタリ重なりあった。
「ちょ、ちょっと待ってください。頭が混乱してしまって」
「ゆっくりお考えください。コーヒーでも持ってこさせましょうか」
「いえ、けっこうです」
単なるお礼とはいっても臓器売買になるのではないか。移植当事者間に金銭授受やそれに類似する行為があった場合は双方ともに罰則の対象になる、と臓器提供者保護法ができたとき、テレビのニュースではさかんにそういったことを捲くしたてていた。
そんなことをやったら、兄が嘆き悲しむのではないか。いやいや、兄の意志は心臓を捧げることにあって、そのほかのやりとりにはこだわらないはずだ。問題はあくまで提供するか否かであって、それからあとの出来事に兄がとやかくいうはずはない。
それからなおしばらく考えんだあと、天井を仰いで深呼吸をした。
「ふっー、外部に漏れるようなことはないでしょうね?」
それまで強ばっていた教授の口元が緩んだ。
「だいじょうぶです。私と一部の関係者だけが知ることです」
そして、すかさず電話をとって告げた。「ああ、私です。事務長、例のものをすぐ持ってきてください」
ほどなく口髭を生やした、小太りの男がやってきた。良次に軽く会釈すると一枚の封筒を教授に手渡し、ものも言わず出ていった。
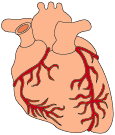
「どうぞ、お改めください」
教授は封筒から小切手を取り出すと、ニヤッとして良次に差し出した。
小切手を受け取る手が、心なしか震える。目線をさらっと数字の上に走らせ、上着の内ポケットに持っていく。だが、なにかおかしい。二つめのカンマの左側に、“20”となければならないのに“2”とだけしかないのだ。
もう一度確かめてから言う。
「これでは話になりませんね。白紙に戻しましょう」
良次は、小切手をテーブルの上に放り投げた。
「先ほどお約束したものですが、なにか?」
「ゼロが一つ足りませんよ」
「そんな・・・」
教授は、良次を唖然とした目で覗きこむと、ソファの背もたれにどっと寄りかかり、深い溜息をついて言った。「しばらく時間をください。右から左へという金額ではありませんので、部長とも相談してみます。ここでお待ちになっててください」
教授は小切手を無造作にポケットにつっこむと、足早に出ていった。
吉と凶と出るか、こうなれば腹をくくって待つしかない。だいたいにして、私大医学部の教授が百万単位の金額を出してくるとは思いもよらなかった。
コッチ、コッチと、壁時計の秒針音が必要以上に耳に衝く。待つこと三十分、教授が渋い表情で現れた。
「これを見てください」
そう言って新しい小切手を差し出す。今度はひとケタ増えていたが、“2”の数字は“1”に変わっていた。
良次はなにも言わず、腰を浮かした。
「まあ、私の話しも聞いてください。菊池さんのご希望に添いたいのは山々なんですが、今の私たちにつくれる金といったらこれが限度なんですよ。それで不足分を補うに、私たちにもお手伝いできることはないか、という話しになりましてね。いろいろ検討してみたんです」
顔をそむけたままとりあえず腰を下ろした。
「賠償金のことなんですが、少しでもその額を増やすようにすれば菊池さんの取り分も少しは増えるだろうと思うんです。それで」
「待ってください。賠償金は、僕には関係ありませんよ」
教授が怪訝そうな顔で訊く。
「お兄さんご夫婦は子供さんはいらっしゃらなくて、ご両親もお亡くなりになってるということでしたね?」
「そうですが」
「ご兄弟はお兄さんと菊池さんの二人だけなわけでしょう?」
「ええ」
「それでしたら菊池さんにも入ってきますよ。相続法の詳しいことは私にもよくわかりませんが、配偶者に四分の三、残りの四分の一を兄弟が相続するはずです。兄弟は菊池さん一人しかいないわけですから、その四分の一がまるまる入ってくるわけですよ」
「はあ、そうなんですか」
これは耳寄りな話しだった。賠償金は義姉にだけいくものとばかり思っていたのだ。
「それでお兄さんはこれまでのところは働ける見通しはまったくたっていなかったわけですが、細野君にいっていつでも働ける状態で仕事も探していたと、保険会社に証言させるようにしましょう。今のままでは賠償金はたいしたものは出ないでしょうからね」
聞きながら、それはそうだと胸の内で相槌を打つ。
「それから事故処理をしているH署の署長は私の知り合いでしてね。現在のところ飛びこみ自殺の線が濃厚のようですが、これも署長にいって百パーセント運転者の過失ということにしてもらいましょう。なに、それでなくても人身事故は物損事故と違い、被害者に有利に解釈するのが普通なんですよ。残された奥さんの窮状を話せば、もともと物わかりのいい人ですからね。簡単にわかってくれますよ。事務長は賠償問題には詳しいんですが、この二つがあることで算出額が二倍から三倍に跳ね上がるだろうとのことです。最高額で一億ですから、かなりのものが期待できると思いますよ」
それなら四分の一としても二千万前後にはなるだろう、と良次のカンピューターが勝手に計算する。
「世のため人のため、そして菊池さんのため、なによりもあとに残された奥さんの生活のためにもここはひとつ、ご理解ください」
教授は懇願調になって言った。
ドナー登録は、動機はどうあれ、兄自らの意思でやったのは動かし難い事実だ。そして、その結果を積極的に活用したい人がいる。心臓提供を拒んだところで、兄が生き返るわけでもない。教授のいうとおり賠償金はより多いほうが義姉の生活も楽になる。恩着せがましいことを言われて窮屈な思いをすることもないのだ。
そうだ、みんなのためになることだ。そう思いこんでしまえば結論は出た。
「一つ条件があります。いや、条件ということのほどでもないんですが小切手ではなく現金でお願いします。それと、いま先生の言われたことは全面的に信用するとして、領収書とかの書類のやりとりは一切しないことにしましょう」
「なるほど」
教授は含み笑いを浮かべ、上目使いに良次を見る。「きょうはもう銀行が閉まってますから無理として、明日の昼までには用意させましょう」
「それと手術までには、あと二日はください。義姉には最低でもそれぐらいの時間は必要ですから」
「わかりました。その程度なら問題ないでしょう。お兄さんのためにも必ず成功させますからね。さあ、これで忙しくなるぞお」
教授は肩をぐるぐる回し、背伸びをして軽い柔軟体操を始めた。それに調子を合わせるかのように、プルルルンと机上の電話が鳴る。
「なに、ほんとうか。すぐに蘇生術を始めたまえ。私もすぐにいく」
教授の顔はとたんに険しくなった。

|

|

|

|

|