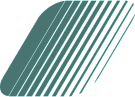

4 悲鳴
「なにかあったんですか?」
「奥さんが、わけのわからないことをわめき散らして人工呼吸器をはずしてしまったそうです」
「えっ!」
良次はソファから飛び上がると、そのまま廊下へ飛び出した。
義姉は思っていたよりは冷静に対応しているように見えていたが、そうではなかったようだ。ここで心臓を止められ、移植に使えないようなことになったら、いま話しをつけたことのすべてが水の泡となってしまう。
二階のフロアーに降りると、義姉が二人の看護婦に腕をとられ、個室のほうに連れていかれるところだった。
義姉が良次に気がつき、看護婦の手を振り解こうともがきながら甲高い声を張り上げる。
「良次さん、だめよ。こんなところにおいちゃ。なにもしないまま、秀一さんが殺されちゃうわ」
「そうじゃない。もう死んで・・」
常軌を逸した義姉に、なにを言ったところで始まらない。「わかった、わかった。とにかくあとは俺に任して、義姉さんはしばらく休むといいよ」
「だめ、あの人には私がついてないといけないの。あんなものより私のほうがずっといいはずよ」
「えっ!?」
錯乱状態とはいえ、背筋をズキッとさせられるものがあった。
あとからきた教授が若い医者に言う。
「山内君、鎮静剤を」
すかさず山内と呼ばれた若い医者は看護室にむかう。
「さあ、部屋にいってよこになろう」
良次も後ろから抱きつくように、というよりも、羽交い締めにするような格好で個室に連れていく。
「痛い、放して。秀一さんといっしょにいるの」
「落ち着いたらいくらでもいっしょにいれるよ。薬を飲んでひと眠りしないと」
引きずるようにしながら、どうにか部屋に中に入った。ベッドに寝かしつけるのもひと苦労だ。
「いや、いやあ。やめてえ〜」
あらん限りの力を振り絞って抵抗する義姉を押さえつけるのは、なんともやるせない。だが今はこれしかなかった。
「腕だけは動かないようにしてもらえますか」
若い医者が注射器を上に向け、液をピッと出すと、表情ひとつ変えずに注射した。
「痛い、いた〜い」
義姉はそれまでにも増して、病棟中にまで響き渡るような大きな悲鳴をあげたが、注射をしてすぐにジタバタしていた手足が静かになり、さらにものの数十秒とせずに義姉は力抜けて眠りについた。
良次が義姉から肘打ちを食らった頬を擦っていると、看護婦が気の毒そうな顔をして言った。
「大変ですねえ」
看護婦と若い医者が出ていくと、入れ替わりに教授が入ってきた。
「ふう、どうにか回復しました。あのまま心臓が止まるようなことがあれば、殺人罪に問われかねないところですよ」
「はあ? もう死んでるんじゃなかったですか」
「い、いや、それはそうですが、呼吸器をはずすのは医者がやることになっていますからね。遺族が勝手にやったとなれば法律上の問題が生じます」
臓器提供者保護法どころか刑法もろくに知らない良次は、そんなものか、と思うだけだった。
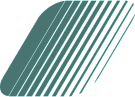

「義姉のことなんですけど、細野先生にいってこのまま精神科病棟に入院させていただけないでしょうか。僕の手には負いかねますので」
「そうですね、それがいいでしょう。さっそく細野君にこさせるようにしましょう。こうなったことでもありますし、もう待つ必要はありませんね?」
「ええ。臓器を摘出した跡は、できるだけ残らないようにしてもらえませんか」
「わかりました。抜い合わせるのは形成外科の者にやらせましょう。でも、おのずと限界はありますよ。もっとも奥さんのこのようすでは葬式に出るのもむずかしいんじゃないですか。先に荼毘に付してしまえば、それまでのような気がしますけど」
「ふむ、そうかもしれませんね。遺体はいつ返していただけるんですか?」
「これから準備に入って、明日の朝から始めます。摘出自体にはそれほど時間はかかりませんから、昼までには運び出せるかと思います」
「それと、例のものも昼までに忘れないでくださいよ」
薄笑いで念を押すと、教授も薄笑いで答えてくる。
「だいじょぶです。すべて事務長に任せてありますから、わからないことがあったら事務長に訊いてください」
「わかりました。僕も先生も兄には感謝しなければいけませんね。移植手術が一段落ついたら線香の一本ぐらいはあげにきてください」
「もちろんですよ。それと奥さんのことですがこのようすだとしばらくは、いや、ひょっとすると一生を精神病院で終わることになるかもしれませんね。身寄りがまったくいないということですから、禁治産の指定を受けられて菊池さんが後見人に収まればよろしいんじゃないですか。そうすれば大手をふって賠償金の全部を菊池さんの好きなようにできるんじゃありませんか」
禁治産か準禁治産の宣告を受けるというのは、兄が勝手に借金をつくったときに両親が検討したことがある。だが結局は、そのことに兄がよけいに甘えることになってもいけないし、一方では下らない屈辱感を与えてしまうことになりかねないということで立ち消えになった。
それを血もつながっていない良次が義姉の後見人になるなどと、いくらなんでもおこがまし過ぎる。
「いえ、そんな立場にはありませんよ。つまらないことを言わないでください」
「いや、これは失敬。それじゃ、これから準備にかかりますので」
もう五十は過ぎているだろうに、ユッサユッサ歩く身体はまるで年を感じさせなかった。
これで義姉を病院に入院させておけば、なんの手間もかからない。あとは葬式を出して兄を弔ってやるだけだった。
廊下で一服していると、ICU室への人の出入りが急に慌ただしくなった。たいていが医者の卵か、学生と思える二十代の連中だ。終いにはICU室の中がいっぱいになり、廊下から背伸びしながら見ている者まで出る始末だった。
元来大学病院というところは患者がモルモット的になってしまう要素がある。理解してはいても弟には辛い光景だ。部屋の中に入って義姉に付き添っていることにした。
それから少しして、精神科の細野教授が、男の看護士二人を連れだって現れた。
「その節はお世話になりました」
兄が最初精神科にかかったとき、弟の立場からということで良次も一度外来に呼ばれて兄のことについていろいろ聞かれたのだった。
「静かに眠ってますね。だいぶにぎやかだったそうじゃないですか。事情はすべて江畑教授から伺ってます。このまま精神科病棟へ入院させましょう」
「そうしていただけると助かります」
細野教授は看護士に、義姉をストレッチャーに移すよう指示した。
「この先、独りで生活は無理かもしれませんね。入院してまた誰か、見つかるといいですが。まあ、ご心配はなさらずにこちらにお任せください」
「よろしくお願いします。あのう、それで義姉にはしばらくのあいだ新聞、テレビは見せないようにしていただけないでしょうか」
「閉鎖病棟には、そういったものは一切ありませんからご懸念には及びませんよ。それにしてもよく決心してくれましたね。私もできるだけのことはしますからね」
「ええ、よろしくお願いします」
また深々と頭を下げる。江畑教授には多少大きな態度に出れても、細野教授にはひたすら頭を下げるしかなかった。

|

|

|

|

|