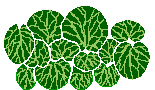
2章 密かな楽しみ
自転車に乗って図書館にいく道すがら、良次は一年のときにもこれと似たようなことがあったのを思い出した。良次の高校で行われた文化祭で、見物にきていたY高校の女子生徒三人と、それに良次と青柳の五人が話す機会があった。せっかく知り合ったのだから、あとあとグループ交際をしようということになり、女の子との交際の経験のない良次は有頂天になったが、三人と別れたあと青柳は、
「俺はグループ交際ってのは性に合わないから、あのうちの一人と付き合うよ」
と言ってきた。がっかりしている良次をなぐさめるように青柳は言葉を続け、
「おまえもあのうちの一人と付き合ったらどうだ。どの子がいいんだ?」
と言うので、そのうちの一人の名前を言った。
青柳が気に入った子とは別の子で、
「それじゃ、向こうと話しをつけて逢う手はずを整えてやるからあとはうまくやれよ」
と、いうことになった。
良次は、それはそれでいいと思った。青柳ではないが、グループ交際よりは特定の彼女ができたほうがいいにきまっていた。
その後一日千秋の思いで、青柳から相手との約束を取り付けた旨の返事を待ったが、催促しても生だら返事ばかりで、一向にらちが明かなかった。そしてしばらくして、青柳はある日突然にとんでもないことを言ってきた。
「実はおまえがいいって言った子と、ずっーと付き合っているんだよ。悪いなあ」
なんてヤツだ、と腸(ハラワタ)の煮えたぎる思いだった。
「最初におまえのことを話したら、おまえのことは眼中になくて俺が好きだって言うんだよな」
と、はっきり相手が良次のことをなんとも思っていないことを聞かされ、さらには
「俺が気に入った子はきまった男がいるって言うしさ。よくよく見たらかわいいんだよな。女の口から好きだって言わせておいてほっといたら、それこそ男がすたるってもんだろう」
などと、大人びたキザなセリフを並べられては、黙って諦めるしかなかった。しかも青柳はその子とは一年と続かず、ほかの女子高校生に乗り換えるのを見ていては、どうやったらあんな気楽にナンパできるんだろう、とただ指をくわえて眺めているしかなかった。
今回もあのときの二の舞になるような気がしてならない。鳶に油揚げをさらわれるではないが、セーラー服の彼女を青柳に教えたところで、良次にはいい目を見られそうにないのだからこのまま家に帰ろうか、直接声をかけられなくても一人片想いにふけっていてもいいではないか、などと思った。
はたまた、いやいっそのこと彼女にのめりこませて、あいつが女にうつつを抜かすあいだにこっちがいい成績をあげ、推薦の競争相手を一人でも蹴落すいいチャンスではないか、などと打算的な考えも渦巻いてくるのだった。
そうこうしているうちに、良次の迷いとは無関係に図書館に着いてしまった。
「きてるかなあ。楽しみだな、おい」
青柳は、勉強のことはどうでもいいような様子で良次の肩を叩き、スタスタと元気よく先にたって図書館の玄関をくぐった。
(ノーテンキな奴め!)
なぜこんな軽いやつとどっこいどっこいの成績でいなければならないのか、神様を恨んだ。
カウンターでロッカーの鍵を受け取るとき、おばさんはいつものようにニコッと愛想笑いをして渡してくれたが、良次には昨日のことを意識して、からかわれているような気がしてならず、おばさんとは視線を合わせられずに口許を見て通った。
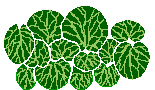
自習室に入ると、さっそく青柳が小声で訊いてくる。
「おい、どうだ。いるか?」
「うん・・・」
どこの高校も試験の時期のせいか、高校生の姿がやたら目立ち混んでいた。空いた机を探すふりをして自習室全体に目をやった。セーラー服の女子高生は十数人はおり、そのうちT学園の生徒は三人だけで、その中におさげ髪の子は一人もいなかった。二度、三度と見渡してみたが、やはり昨日の彼女はいなかった。
「おい、どうなんだよ?」
青柳がいらついて、さきほどよりは少し大きめな声で訊いた。
「残念だな。きてないようだよ」
「ちぇっ、しょうがねえな。勉強でもするか」
「図書館は勉強するところなんだよ」
良次の言葉が耳に入らないのかのように、無視して窓際の空いた席に向かっていってしまった。
(うらやましい奴だなあ)
中学校のときから近くで青柳を見てきて、どうしたらこういう性格になれるのか、といつも考えてきたが、高校になってからはやっと人それぞれに性格と生き方があるさ、と割り切れるようになった。それでもこういった出来事があると、劣等感とまではいかないまでも、人間としてのレベルの差を感じさせられた。
それにしても彼女がいないのには、安心したようながっかりしたような気分だった。つい、青柳にのせられて図書館にきたものだから勉強が手につかず、しばらくはボオッーとしていた。周囲の人の手前、明日の試験科目の物理の教科書を机に広げてはいたが、活字を追えず肘鉄をついてぼんやり見ているだけだった。それに引き替え、右斜め方向にすわっている青柳を見ると、なにやらせっせと鉛筆を動かし勉強に余念がないようだった。こうなると、蹴落されるのは自分のほうか、と自嘲ぎみの笑いがこぼれる始末だった。
気を取り直し、物理の練習問題を解くことに専念した。勉強にもう一つ身が入らぬときは、教科書やノートを見直すよりも問題を解くようにしたほうが、自然と夢中になることができるのだった。一ページ分をやり終え、ふっーと深呼吸と背伸びをして何気なく左隣りの机にすわった女の子を見ると、その子がやはり同じように背伸びをして顔を上げた。
思わず、アッと声をあげそうになった。例のセーラー服の彼女だった。偶然視線が合って彼女のほうも気がついたとみえ、お互いに慌てて視線をずらした。セーラー服ばかりに頭がいってしまっていたが、きょうの彼女は私服姿だった。しかもおさげ髪ではなく、ナチュラルに垂らしたままの姿で、セーラー服とはまた違う清潔感あふれるイメージを漂わせていた。
青柳に教えてやるつもりで席を立ち青柳に近づいたが、目の前まできて気が変わった。
「何だよ?」
怪訝な顔で見上げてくるのを無視し、そのまま通り過ぎてトイレにいった。見てて眺めるだけの片想いでもいい、あんな子を青柳の毒牙にさらさせてなるものか、と思った。気のせいか、小便の出もいつになく快調だった。
席に戻ってからも、彼女をちらちら見ながらの勉強は楽しかった。昨日とは違って、机が離れているせいもあってか一人舞上がることもなく、練習問題もどんどんかたずいていった。現金なもので、今度の試験は十番以内に入れそうな気さえしてきた。青柳は彼女のことに気がつくはずもなく、一人もくもく机に向かっていた。
(ふん、ざまあみろ!)
良次は自分だけが彼女を楽しめることに優越感を覚え、女のことに関しては青柳の足下にも及ばなかったが、きょうだけは勝った、と思った。そもそもよけいなことを青柳に教えなければつまらぬ神経を使わずにすんだのだが、それでもなにかしら儲けた気分で勉強を続けることができた。
ときおり息抜きの合間に彼女のほうを見ると、隣りに座ったS女学院の制服を着た女の子とこそこそ話しをしていた。
(友達なんだろうな)
よく見るとその子もなかなかの器量よしで、ちらちら眺めているうちに二人とも自分の彼女にしたような気分になった。そして青柳のほうを見ては優越感にひたるのだった。
物理の練習問題はすいすいかたずいて、次に電子工学の教科書を開いて勉強を始めた。その合間にも彼女に視線をやるものだから、その何度かは彼女と視線が合ってしまい、彼女も見られているということに気がついて、慌てて目を下に落とすのだった。
(私服姿だからこの近くに住んでるんだろうな)
などと楽しい連想と試験勉強は、彼女が帰る夕方まで続いた。

|

|

|

|

|