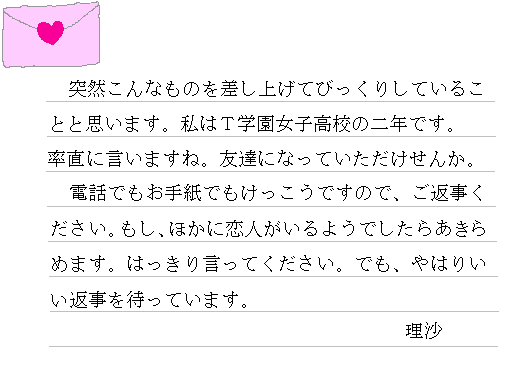
3章 初めてのできごと
中間テストが終わり、一週間経った日の放課後、良次はさきほどホームルームで配られたばかりの、電気科だけの成績一覧表にしげしげと見入っていた。一覧表には氏名は記載されていなかったが、すべての科目の点数と合計点が記入されているので、取った点数から自分がどの位置にあるのか、わかるつくりになっていた。
良次は総合で8番に入っていた。試験一日目はセーラー服の彼女のせいで・・・、というわけでもないだろうが、あまり出来がよくなかったが、二日目、三日目に関しては、まちがいなくいい意味での彼女のおかげで勉強がはかどり、試験のほうも順調にこなすことができた。総合順位がひとケタ台にのったのは、一学期の実力テストのとき以来のことだった。
「よう、また負けてしまったな」
後ろから青柳が渋い表情で声をかけてきた。何科目か答案用紙を見せ合っていたので、お互いに何番かはわかっていた。
「ジツリキだからな、しょうがないさ。悪く思うなよ」
「ふん・・・。この分なら推薦枠に入るかもしれないな」
「いや、推薦対象の試験に入ってからの十番以内は二回目だからな。まず無理な話しさ」
推薦入学の試験は、早い大学では十一月から始まるので、推薦枠の決定もそれに合わせてしなければならず、その資料となる学内試験もあと一回の実力テストだけだった。その試験もうまく十番以内に入れたとしても、平均で十番以内に収まるのはかなり苦しかった。
「ところでさ、彼女元気かよ」
青柳はおどけた顔で、突拍子もないことを訊いてきた。
「なんのことだよ?」
良次はとぼけたつもりはなく、不思議に思って訊き返した。
「おまえ、試験が終わってからも毎日図書館にいってんだろう」
そこまで言われて、良次は別に悪いことをしているわけでもないのに、ドキッとしながら答える。
「ああ、試験が終わってからもなにも、始まるまえからバイトにいく以外は毎日いってるよ」
「例のセーラー服の彼女、会いにいってんだろう」
「ば、ばかなこと言うなよ。おまえといっしょにいってからは、図書館にはきてないよ」
良次は学校の許可を得て、二年のときからファミリーレストランで週に三日だけウェイターのアルバイトをやっていた。試験に入ってからは休みをもらっていたが、試験が終わってからもこの一週間は適当な理由をつけて、きょうまで続けて休みをとっていた。もちろん図書館にいくためで、一日もかかさず通っていた。
「ま、いいけどな。もう俺には教えてくれそうにないな?」
「教えるもなにも、図書館にこないものを教えようがないだろう」
「ふーん、そこまでとぼけるとなると、もうモノにしたってことか?」
疑り深い目でにらんでくる。
「つまんないこと言うなよ。俺は野暮用があるから先に帰るぞ」
いつまでも青柳の相手をしていると、よけいなことをしゃべらさせるようだったので、鞄をもってそそくさと引き上げる。
「きょうも図書館か?」
後ろは振り返らずに、左手を横に振った。「そうか。いや、いっしょにいこうかと思ったもんだからな」
(なにっ!)
良次は思わず立ち止まりそうになったが、それでは青柳がカマをかけたのに見事にはまってしまうと思い、知らんぷりしてそのまま立ち去った。
校門を出た良次は、図書館に向かうべきか否か迷った。青柳には、いかないと言ったてまえ、むこうでバッタリ顔を合わせたのでは立場がないし、かといって家にまっすぐ帰るのも気がすすまず、バイトも休みをとってるしでどこにもいきようがなかった。
自転車をこぎながら、どうしようかと思いながらも行き先は図書館に向いていた。図書館の前まできて青柳と出くわすようなことがあったら、用事を終えてからきたんだ、とでも言い訳をすることにして中に入った。
自習室の入り口に立つと、空いた席を探すのよりも先に彼女がきてるかどうかを見るのが、すっかり習慣になってしまっていた。
(いたいた。きょうはセーラー服か)
窓際の端のほうに、たまにいっしょにいるS女学院の女子校生と向かい合ってすわっていた。同じ机にすわったのでは、肝心の勉強に身が入らなくなるので、机を二つほどあいだにおいて、しかも彼女が正面に見える机に陣取ることにした。
彼女があとからきたときには、良次のほうが席を変えたのではあまりに白々しいので、そうそう都合のいいようにはいかなかったが、彼女が先にきている分には、良次の好きな位置の机にすわることができた。この十日あまりで身につけた、生活の知恵だった。
席に腰を下ろすとき彼女を見ながらすわったが、そのときちょうど彼女も顔を上げて、二人の顔が正面にピッタリ合ってしまった。すると彼女は、良次に会釈でもするかのようにはにかみながら顔を下に向けた。まるで知った人間に挨拶でもしているような仕草だったが、良次は自分の気のせいだろう、とは思いながらも悪い気はしなかった。
さらにそのあとも様子を伺っていると、向い側の友達と笑いを噛み殺すようにして、クスクスやっていた。自分の顔になにか付いているのか、と気になったがわかるわけもなく、勉強道具を机に広げた。
きょうは試験の時期も過ぎ、人が少なくなったせいで空席が目立ち、彼女と良次をさえぎる障害物がなにもなかった。
(ちょっと近過ぎたかなあ)
彼女からまともに見える位置にすわってしまったものだから、いっしょうけんめい勉強をするポーズをとってはみたものの、さっき笑われたことが気になり、顔を鏡で見るつもりでトイレに立った。
さんざん鏡で自分の顔を見渡したが、別にどこもおかしいことはなく、失礼な子だなあ、などと思いながらトイレを出た。出口の扉を開けると横に、なんと彼女とS女学院の子が二人して立っており、腕には鞄を抱えていた。
(なにをしてるんだ、こんなところで?)
変に思いながら、すっーとその前を摩り抜けようとしたが、二人が良次の行く手をさえぎるように前に立ちはだかった。そして、彼女がピンクの封筒を良次に向かって突き出したのだ。
「あの、すみませんけど、これ、あとで読んでください」
「は、はい!?」
とにかく目の前を通せんぼされて封筒を出されたのだから、受け取る以外にはなかった。二人は「きゃ!」と小声をはりあげ、手をとりあって小走りに駆けていった。
一瞬なにがどうなっているのか、さっぱりわからなかった。まさか、これはラブレターというやつか。いや、そんなことがあるわけはない。とするといったいなんなんだ・・・。
驚きのあまり良次は足がすくんで動けなかった。間をおいて、フッーと深呼吸をしたあとトイレに引き返し、洋式の便器に腰を下ろした。おそるおそる震える手で封筒を切り便箋を開くと、そこには彼女のしなやかな手にそっくりの文字がしたためてあった。
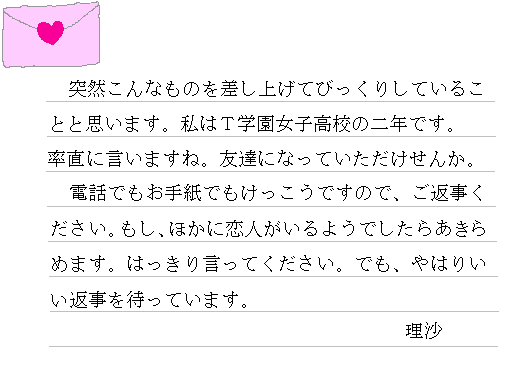
(やったー、ラブレターだ! 理沙っていうのか)
良次は夢を見ている気分になり、興奮からくる熱さが身体中を覆う。生まれて初めての出来事だった。二枚目の便箋にはフルネームと住所、電話番号が記されてあった。

|

|

|

|

|