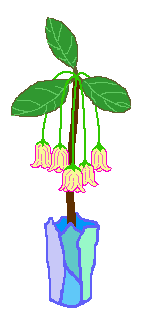
5章 にくめない奴
K公園には約束の時間より、一時間も早く着いてしまった。ウィークデーの午後はあまり人影は見られなかったが、土曜日のせいか屋台の店も出て、若いカップルがあちこちで憩いのひとときを過ごしていた。
理沙にはあれからすぐに、「土曜日にこの公園で逢いたい」という内容の手紙を書き、理沙からは折り返し速達で、「まちがいなく伺います」との返事をもらっていた。もっと早い時間にと思ったが、理沙が美術クラブの会合があるとかでこの時間になった。
最初のデートはどんなところでしたものか、さんざん迷ったあげくにK公園に決めた。初めは街中の繁華街にでも出て、気のきいた喫茶店にでも入って話しこもうかと考えたが、あまり慣れない場所にいって恥でもかいたら、元も子もないと思い、図書館近くのK公園としたのだった。理沙の住所から察するところ、図書館からの帰り道となるはずだし、良次にとっても学校から図書館にいく道筋にあたっており都合がよかった。
公園全体を見渡してみても、当然のことながら理沙の姿はまだ見えなかった。遅れでもしてぶちこわしになったら大変と思い、また学校でぼっーと時間を潰しているのも脳がなさすぎるので、予定よりずっと早くきてしまった。
図書館にはあれ以来、まったく足を運ばなくなっていた。きちんとした形で理沙と逢わないうちからばったり図書館で顔を合わせてしまったら、それこそバツが悪いと思ったからだ。きょう逢えばあとあと図書館でいっしょに勉強できるかと思うと、ますます楽しさがつのってくるのだった。
まだしばらくはこないだろうと思ってベンチに横になっていると、そばに人影ができた。
「すみません、遅くなって」
理沙だった。良次は慌ててベンチから飛び起きた。
「い、いえ、僕のほうが早くきただけのことですから」
きょうはきちんと髪を二つに分けておさげ髪の姿だった。やはりセーラー服のときはおさげ髪のほうが似合っていた。普段、通りで見かけるセーラー服姿はどうということはなかったが、まのあたりに見るセーラー服の白さは眩しかった。
「この前はびっくりさせてすみませんでした」
「い、いえ・・」
心の準備ができていなかったせいで、なにを話したものか言葉に詰ってしまった。「ここにすわりませんか」
「はい」
理沙はこっくり頷くと、良次の左隣りに腰を下ろした。香水の香りか、それとも単なる石鹸の匂いなのかわからなかったが、理沙からは良次の頭をポワーンとさせるに充分な香りが漂ってきた。
「図書館にはいつもきてるんですか?」
「いつもってわけじゃないですけど、試験のときとか、時間があるといってます」
「よくいっしょにきてるS女学院の人がいるでしょう。仲のいい友達なの?」
「ええ、そ、そうです」
どういうわけか理沙は、答えにくそうにつまりながら言った。
「あの、私のほうが年下ですし、あまり丁寧に話されるとかえって話しにくいですから、良次くんの」
理沙はそこまで言って、話すのを止めた。
「え、なに?」
「あの、良次くんって呼んでいいですか?」
理沙は肩をすぼめて、ちょっぴり舌を出して訊いた。
「ええ、いいですよ」
年下の子から、「くん」で呼ばれるのには多少抵抗があったが、それもかわいらしくて、またそれだけすぐに仲よくなれるのでは、と思った。
「あらたまって話されると、私のほうがしゃべりにくいですから、お友達と話すような感じでしゃべってくれていいです」
それは良次にしても同じことなのだが、初対面からそう慣れ慣れしく話すわけにはいかなかった。
「そうですね。気をつけますから。あっ、これがいけないのか。はは」
「うふふ、良次くんておもしろい人なんですね」
「理沙も・・。あの、呼び捨てにしてもいいかな?」
「ええ、遠慮なく」
「それじゃ、理沙も普通に話してくれていいよ。やっぱりよそいきの話し方じゃ疲れるものな」
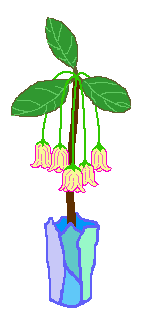
良次は、これなら充分気が合いそうだな、と思った。
「ええ、良次くんは進学するの?」
「うん、するよ。志望はどういう学部だと思う」
「電気科なんだから、理工系の大学でしょう?」
「電気科は高校だけで卒業して、大学は法学部に進むつもりなんだ」
「ええ、どうして? 随分違った道にいくのね」
「たいした理由はないけどさ。電気は嫌いじゃないんだけど、仕事にするまではいかないんだな。ちょっと法律の条文を見る機会があってそれから好きになってさ。それじゃ法律の道をいってみようか、なんてさ」
「ふーん、大学はどこにいくの」
「東京のN大さ。あそこなら推薦入学もやってるし、推薦してもらえなくても一般受験で入れそうだからさ」
すると理沙は、幾分淋しそうな表情になって訊いた。
「そう、東京に出るの。地元に残る気はないの?」
「残ってもいいけど、県内にある法学部のある大学は二つしかないしさ。どっちも俺の頭じゃ九十九パーセント無理なんだな」
「そうなの。将来は弁護士さんになるとか?」
「いくらなんでもそこまでは無理だな。ま、法律っていったっていろいろ仕事はあるから、あまりむずかしくないようなのを選んでやってみるつもりさ」
「先のことをきちんときめてるなんてすごいわね」
理沙は視線を下に落とし、なにか悩み事でもあるかのような仕草をした。
「理沙は決めてないのか?」
「うん、おかあさんは短大ぐらいいきなさいって言うけど、私は卒業したらすぐに働こうと思ってるの」
「親が短大にいけってことは、経済的には問題ないってことだろう。なのにいかないってのは、俺にいわせたら贅沢だけどなあ。我が家はマルビだからさ、入学金をつくるにも四苦八苦だよ」
「マルビって貧乏ってこと?」
「うん、もう死語かな。ハハ。親の稼ぎが悪いから、ほんとなら大学なんていけないとこでさ。だから工業高校に入って卒業したら即就職のつもりだったんだ。でも大学いきたいって言ったら、一年目の分だけ出してやるってことになってさ。だから、あとは自分でやらないとな」
「ふーん、偉いのね。うちは経済的には困ってないけど、あまり親の世話にもなりたくないのね。なるべく早く独り立ちしたいっていうか。良次さんのとこと逆だとよかったのにね」
「そうだな、世の中うまくいかないもんだな」
そのとき公園の脇を通る小道から、大きな声で挨拶をしていく者がいた。
「センパーイ、どうも。コンチハ」
二人は何事かと思い、同時に振り返った。
「あのバカ」
「後輩なんですか?」
「いや、悪友っていうやつ」
青柳だった。(最近はとんでもないところで現れる奴だなあ)
自転車の方向からすると図書館から帰るところらしいが、青柳がここを通るのをすっかり忘れてしまっていた。
「センパイ、邪魔してしまったようですみません」
(うるさい、黙って通れ!)
良次はそっぽをむいて知らんぷりを決めこんだ。
「ふふ、友達もおもしろい人なのね」
理沙には受けがよかったのが、せめてもの救いだった。こんなことが原因で理沙とうまくいかないようなことがあれば、青柳を一生恨むところで、K公園を選んだのは失敗のようだった。
「今さ、週三日だけどファミリーレストランでバイトやってるんだ。理沙もなんかやってる?」
「うーん、やりたいなあとは思ってんだけど、まだやったことない。お店はどこなの。今度いってみようかな」
「だめだよ、みっともないから。知った人に見られるってのは恥ずかしいもんだよ」
「関係ないでしょう。私の友達にだってファーストフードのお店でやってる子がいて、たまにハンバーグ買いにいくわよ」
「とにかくだめ!」
「ケチ!」
二人はお互いに顔をにらみ合わせて、「あははは」「うふふふ」と笑った。
理沙は一見見にはいいとこのお嬢さんに見えるので、根っから貧乏人育ちの良次とはフィーリングが合うかどうか心配だった。やはり見かけだけで人は判断できないもので、話しが合わないというようなことはなく、良次は一安心だった。これなら特別むずかしい神経を使わなくても付き合っていけそうだな、と思った。
「ちょっと歩こうか」
「うん、川添いにいってみない」
公園の中には、わざわざポンプで汲み上げた水を流している人工の小川があり、それと並行して遊歩道が続いていた。公園の木々が、まだ充分紅葉にはなっていないのにパラパラ舞い落ちるのは、初秋になったことを示していた。西の山にはほんの少し陽がかかり、空をほんのり紅く染め、立ち上がった二人の影法師も、ひところよりずっと長くなっていた。
ちょうど二人が歩く向こうから、同じような高校生のカップルがやってきた。見ると、生意気にも女の子のほうが、男の腕をとって横から抱き付くようにして歩いていた。良次は、よしそれならと思い、えいっとばかりに理沙の手を掴んだ。こわくて理沙の顔は見れなかったが、なんの抵抗もなく理沙もそっと握り返してきた。柔らかでほっとさせるような感触で、女の肌はゴツゴツし
た母のものしか知らない良次には、とても刺激的でさえあった。青柳が言った、「好きになったら、したくなるものさ」の言葉の意味が、良次にもなんとなくわかるような気がした。

|

|

|

|

|