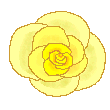
7章 意外な秘密
「良次くん、大丈夫?」
「えっ!」
驚いて後ろを振り返ると、息を切らせながら近寄ってきたのは、理沙だった。
理沙のあとからは、警棒を右手に持った警官がほんとについてきていた。
「びっくりしちゃった。良次くんだなあと思って見てたら、けんかが始まるんだもの。おまわりさんが通りかかってよかったわ」
「白い車だったね、ナンバーは覚えてないかな?」
警官が手帳を開き、メモをとる格好をしながら訊いた。
「ああ、わかりませんけど・・・。たいしたことはありませんから。ちょっと通りがかりの男にからまれただけのことですから」
理沙に知られたくないのはもちろんのこと、父ということがわかれば、当然母にも知らされてしまうと思ったからだった。それにいくら馬鹿な父親とはいっても、犯罪人にまでするわけにはいかなかった。
「君、口から血を出しておいて、たいしたことはないもないもんだよ。知ってる人か?」
「いえ、知りません」
一瞬、ばれたのかと思ってドキッとした。
「それじゃ、詳しいことは交番で聞くからきてください。君もいっしょにきてくれるね」
警官は理沙にも交番所にくるように促した。交番所は広い通りに面した公園の東の端にあった。
「はい、これ」
理沙はそっと、薔薇の刺繍がしてあるハンカチを渡してくれた。いい香りがして、いっぺんに傷が治ってしまいそうな気分になった。
「きょうもきてたのか?」
「うん、ほかにやることがなかったから本を読んでたの。まさか良次くんもきてるとは思わなかったわ。バイトじゃなかったの?」
「これからなんだけどさ、こんな顔していけないな。あとで電話しないとな」
交番に着くとさっそく住所、氏名と学校名、そして相手の人相、風体を訊かれた。
「年齢とか、身長、着ていたものを覚えていることだけでいいですから、できるだけ正確に答えてください」
「いえ、それが急なことだったものですからよく覚えてないんです」
「うーん、なにも覚えてないってことはないだろう」
警官は呆れたように言った。
「ええと、年は五十前後、薄い水色のワイシャツに赤っぽいネクタイをしてました。身長は良次さんと同じぐらいです。あと、 少し白髪が混じっていたように思います」
親切にも横から、理沙がすらすら父の人相を話した。
「いやー、感心だね。君はいい彼女をもって幸せだぞ。髪型はどんなだったかな?」
「普通に七三に分けたものだったと思います」
「ズボンの色はどんなかな?」
「あ、あのー」
良次が、突然二人の話しの中に割り込んだ。もうこれ以上黙っているわけにはいかなくなった。放っておけば、父の手配書が町中に出回るのではと思えたからだ。
「なにかね。まちがったところでもあるかな」
「いえ、相手の男は僕の親父なんです」
「えっー!」
理沙が耳をつんざくような、驚きの金切り声をあげた。
「君ー、これはいったいどういうことかね?」
「すみません。いろいろ事情があって父ということは知られたくなかったものですから」
「どんな事情か知らんが、最初からきちんと言ってもらわないとな」
警官はぶぜんとした表情で、きつい調子で言った。
「はい、ほんとにすみませんでした。ですからただの親子げんかなんで、警察の手を煩わせることもありませんので、これで」
良次は頭を下げ下げ謝った。とにかくいっときも早く交番所を出たかった。
「そりゃまあ、親子げんかをいちいちかまうほど警察は暇じゃないが、今度やるときには家の中でやるんだな」
「はい」
警官に怒られるのよりも、そばで見ている理沙の軽蔑してるととれるような目付きが良次には堪えた。
「じゃ、お母さんに連絡をしてここに迎えにきてもらいなさい」
警官はそう言って、電話器を良次の前に置いた。
「えっー、それは困ります。自分の二本足で歩いて帰れますから」
「なにを言ってるのかね。未成年者がけんかで怪我を負った者を、身元引き受け人なしで帰せると思ってるのかね」
「でも、お袋に知られたらまずいんです」
「どういうことかね。わかりやすく説明してくれないか」
こうなったら観念してなにかも話す以外にはないと思った。
「実は母と父は離婚してまして、僕は母といっしょに住んでいるんですが、きょう父と会ったのは母には内証なんです」
「ふーん、複雑な家庭の事情があるようだが、このまま一人で帰すわけにもいかないしなあ」
警官はいかにも困ったという顔をしながら、腕組みをして椅子に背をもたれた。するとさきほどとは違って、いくらか穏やかな目付きになった理沙が口を開く。
「私のお母さんじゃだめですか?」
警官は警察官特有の人を観察するときの鋭い視線で、理沙をしげしげと眺め渡した。
「そうだなあ。君もたまたま居合せたわけだし、それでもいいかな。ほんとに君はいい彼女をもってよかったな」
それまでの硬い表情とはうって変わって顔面を崩し、ニヤッとしながら良次を向いて言った。
さっそく理沙は受話器をとって家に電話をかけた。こんなことで理沙の母と顔を合わせるのは気が重かったが、贅沢は言ってられなかった。
「そうじゃなくて、私がけんかしたわけじゃないの。だから良次くんとお父さんが・・・、うん・・・。そう、そうなのよ。誰か身元引き受け人が必要なのよ。そう、だからすぐにきて。うん、じゃ待ってるから」
理沙の母も、交番所から電話をしていると聞いては、相当びっくりしたに違いなかった。それでも迎えにきてくれるようで、理沙は受話器を置くと、良次に向かって片目をパチンとやった。
「あの、学校のほうへは連絡するんでしょうか?」
「君が暴行事件を引き起こしたってわけじゃないからな。特に連絡することはないよ」
学校に連絡がいったところで問題にされるとは思えなかったが、それでもいろいろなことを根堀り葉堀り訊かれることはまちがいなかった。
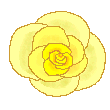
十分もせずに理沙の母は、タクシーに乗って駆けつけた。
「お母さん、サンキュウー」
「まあなんでしょう、この子は。どうもこの度はいろいろご迷惑をおかけしました」
理沙の母は警官に向かって、深々と頭を下げ礼を言った。いくら理沙の母とはいえ、自分の家族のことで他人から頭を下げてもらうとは・・・。良次はひたすら恥じ入るばかりだった。
警官がなにかを言う前に、一言理沙の母に礼を言う。
「すみませんでした」
理沙の母はなにも言わず、微笑み返した。なにか言われたほうがかえって楽なような気もしたが、それはそれでうれしかった。
「ま、君も今後は、こんなことにならないように気をつけることだな」
警官は気の毒そうに良次の肩をポンポンたたきながら、三人を送りだした。
「ねえ、バイト先には電話入れなくてもいいの?」
「うん、あとでいいよ」
しゃべるのも気が重かった。適当な理由をつけてすぐにも二人とは別れたかったが、わざわざ迎えにきたもらったことを思えば、良次から言いだすのも気がひけた。これだけ不様なことを知られてしまえば嫌われてあたりまえで、もうこれで理沙とは終わりだなあ、と思った。
「ねえ、お母さん。良次くんと二人だけで話したいことがあるの。先に帰っててくれない」
「まあ、親をじゃまにするなんてひどい子ね。それじゃ、リョウジくんって言いましたっけ。理沙のこと頼みますね」
「は、はい。どうも御迷惑おかけました」
「ふふ、世の中にはいろいろなことがあるものよ。あまり気にしないことね。それじゃ理沙、じゃま者は先に退散しますからね。あまり遅くならないうちに帰るのよ」
「うん、わかってる。お母さん、ありがと」
理沙の母は、ニッコリ一つだけ笑みを残し、通りがかりのタクシーをつかまえると手をふりながら帰っていった。
「理沙・・・。俺たち、もう終わりかな」
「どうして終わりなの?」
「いやになったろう。あんな親父がいるんじゃ」
「アハハ、関係ないでしょう。親は親、子供は子供よ」
理沙の言葉は、良次からしてみれば意外だった。ただかわいいとばかり思っていた理沙の口から、そんな大人びた言葉が聞けるとは思ってもいなかったのだ。
「じゃ、あれか。きょうのことはなにも気にしないでくれるか」
「あたりまえでしょう。変なこと言わないでよ」
と言うなり理沙は、良次の腕にしがみついてきた。
「ちょ、ちょっとここじゃまずいよ。そこの喫茶店でも入ろうか」
もちろん悪い気分ではなかったが、やはり人通りのある道で腕を組んで歩くような自信はなかった。気のせいか、きょうの理沙はいつもの理沙よりずっと大人の女に見えた。
「良次さんには家の中のことをあまり詳しく話してなかったけど、実は私の家にも秘密があるの」
これまた意外な言葉だった。興味津々で身を乗り出すようにして訊く。
「ひょっとしたら吸血鬼の子孫だとか?」
「もう、そんなことしか言えないの。私の家はね、良次さんの家とはまったく逆のつくりになってるの」
「え? 逆というとどうなってるわけ」
「つまり、お母さんとお父さんは子連れ再婚なの。姉弟は三人って言ったでしょう。私はお母さんの子供で、裕美ちゃんと・・・。裕美ちゃんって、ときどきいっしょにいるS女学院の子を友達だって紹介したでしょう。ほんとは姉妹なの、血のつながらないね。裕美ちゃんと弟はお父さんの子供ってわけ」
「へえー、世の中そんなことがあるんだ」
「裕美ちゃんのこと、嘘をついててごめんね。言いにくかったもんだから」
「別に。俺だって同じさ」
「それにもう少し正確なことを言うとね。お母さんとお父さんは、まだ正式に結婚したわけじゃないの。今はみんなが家族として、うまくやっていけるかどうかの試験期間なの。だから平たくいえば同棲中ってわけね」
「ふーん、すごいことやってるんだな。いつごろまでに結論を出すわけ?」
「お母さんには、年が明けるころにははっきりさせたいって言われてるわ」
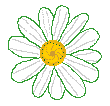
それまでとは少し様子を変えて、雲った顔つきを見せた。
「理沙はお母さんの結婚には反対なのか?」
「そんなことはないけど。みんないい人よ。お父さんもいろいろ気をつかってくれるし、裕美ちゃんとだって仲がいいし、弟はちょっと生意気だけどね、ふふ。男の子はあんなものなんでしょうね」
良次には理沙の言葉が、ちょっと無理をしてるな、と感じられた。
「お母さんと二人だけだと、なにか不都合なことがあるわけか?」
「そんなことないわよ。お父さんが亡くなってから・・・。お父さんってほんとのお父さんのことね。二人だけで仲よくやってきたもの。いつまでもお父さんのことだけ想っててほしいなあとも思うし・・・」
「だったらお母さんに、理沙の気持ちをはっきり言ったらいいんじゃないか」
「はっきりって、ほんとに家の中は全部うまくいってるのよ。それにお母さんが幸せになるのを私に奪う権利なんてないわ。ただ、自分でもよくわからないんだけど、なにか割り切れないものがあるの」
「お母さん、いい人だものな。さっきさ、顔を合わせたとたん娘を変なことに巻き込まないでくれ、とかなんとか怒鳴られるんじゃないかって思ってたんだ。俺のお袋だったらまちがいなくそうなるよ」
「ふふ、お母さんがそんなこと言うわけないわ。ねえ、良次さんもお母さんといっしょに住んでるっていったわよね」
「ああ、そうだよ」
「お父さんと離婚するとき、良次さんの名前はどうなったの?」
「そうか。理沙もお母さんが結婚したら苗字が変わるのを気にしてるんだ」
「うん、だってみんなにわかられてしまうでしょう」
「お父さんが死んでから、苗字は変わったのか?」
「いえ、同じよ」
「それなら大丈夫さ。お母さんが結婚して、死んだお父さんの籍からお母さんの籍を抜くときに、理沙の籍はそのまま残してもらうんだよ。そうすれば理沙の苗字はいままでと同じさ」
すると、理沙は甲高い声で言った。
「ええー、そんなことができるの?」
ウエィトレスやほかの客が一斉に二人のほうを見た。理沙は肩をすぼめおどけた表情で、今度は内証話しをするようにして同じことを訊いた。「ねえ、ほんとにそんなことができるの?」
「できるさ。なにしろ自分のことだから、少し勉強したことあるんだ」
「へえ、すごいわね」
「子供の氏の問題については、民法とか戸籍法にきちんと規定されてるんだよ」
両親がいよいよ離婚となったとき、いかにして自分の名前を変えずにすむのか、家庭裁判所に電話をして訊いてみたり、図書館で六法全書をひも解いて調べてみた。母は始めはいやがったが、父の姓をそのまま使うことで最後は折れてくれた。
「すごいのね。ああー」
理沙がまた奇声をあげそうになったので、良次は慌ててくちびるに指をあて、やっとの思いでそれを制した。理沙はまた小声になって言った。「ごめん。それで法学部志望なんでしょう」
「ピンポーン、法律っていうのはやってみるとけっこうおもしろいんだ。だから進学するってきめたときは、迷わず法学部にしたよ。ま、工業高校からじゃめずらしいだろうけどな」
「ふーん、そういうことってちょっとしたきっかけなのね」
「籍のことは、そのうち折りをみてお母さんに相談してみるといいよ」
「うん、言ってみる」
「その際気をつけないといけないのが、死んだお父さんに籍を残すということは、要は新しいお父さんのほうに移すことを拒否することになるわけだから、お母さんもお父さんも気を悪くする可能性があるということさ。だから相談するときは、理沙の気持ちをよく理解してもらえるように話すことが大事だな」
「うん、お母さんならきっとわかってくれると思うわ」
「そうだな、あのお母さんなら大丈夫だよ」
ふっと通りに目をやると、秋のつるべ落としとはよくいったもので、既に夕焼けも落ち通りには車のヘッドライトが交錯していた。理沙のセーラー服も白から紺色に替わり、秋が日一日と深まっていた。
きょうの父との一件は理沙に嫌われることもなく、皮肉にもお互いの家庭のことを話すいい機会を与えてくれ、それがさらに理沙との親密度を高める役割を果たしてくれた。おかげで父への憎しみが、幾分和らいだことが救いだった。父には、警官に追いかけられたきょうのことはかなり堪えているに違いなく、二度と良次の前には現れないだろうという気がした。
「出ようか。理沙のお母さんに約束させられたものな」
レジでお互いの分の清算をすますと外に出た。
二人には、理沙の発案でお金のかかることは割り勘にする申し合わせができていた。理沙は、友達がお金にまつわることで仲互いをしてしまったことを聞いて、お互いが負担にならない付き合い方をしよう、と言ってきたのだった。
「ねえ、バイト先に電話した?」
「あ、忘れてた!」
「もうだめね。クビよ! アハハハ」
通りには、理沙の快活な笑い声が響いた。

|

|

|

|

|