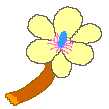
8章 分水嶺
四時限目の授業は、電気科の科長の受け持ちになっていたが、各科の科長と主任とによる合同会議のため自習となっていた。朝から行われている会議は、推薦入学の推薦者を決めるための最終審査であり、授業が終わると同時に事務室前の掲示板に張り出されることになっていた。
既に大枠では決まっているが、推薦する学校側にとっては大学側に対し、あとあとの信用問題もあるので慎重の上にも慎重を重ねて決定する、との説明が昨日担任からあった。以前先輩から聞いた話しでは、大学側からくる受入人数は限られているので、各科の担当者がその枠の取合いを巡って激しい功防を繰り広げるらしかった。
ボーダーライン上に生徒が並ぶと、最後は各科長の力関係によって決まるのだとも聞いた。とすると、電気科の科長は今年からの新任なので、あまりいい情勢とはいえなかった。
当然のことながら良次は、朝から・・・というよりは、この数日は気持ちがそわそわした日々を過ごしていた。成績を見る限り、推薦枠に収まることはかなり苦しかったが、それでもあわよくば、の期待があって薄い望みを託していた。もちろんそれは、推薦入学を希望する者にとっては誰しもが似たり寄ったりの状況であった。
学校推薦となれば、面接試験でよほど非常識な態度でもとらない限り、まず合格はまちがいなく、卒業までは左団扇で暮らせるというものだった。それでなくても就職組はすべて就職が決まっており、教室内は落ち着いて勉強できる雰囲気ではなくなっていた。自習といったところで教科書を机に広げているのは、進学組の一部の連中だけで、それもこの時間の専門科目の教科書ではなく、普通科目の教科書だった。他の者は雑談に余念がなかった。
「よ、滝田。おまえ隣りのクラスの青柳と付き合いがあったよな?」
「ああ」
「青柳からなにか聞いてるかよ」
「なにをだよ?」
「ふーん、じゃ、全然知らないんだな。なんでも彼女をこれにしたって話しだぞ」
左後ろの席にすわっている与田が、そう言って右手で腹のあたりが膨らんだカッコをしてみせた。
「まちがいないのか?」
「ああ、もっぱらの噂だよ。なんでもむこうの親が、この学校じゃどんな教育してるんだとか言って、怒鳴りこんできたんだってさ。下手だよなあ、あいつも」
昨日、帰りがけに青柳と顔を合わせたときには、そんな話題は一言も出なかった。ほんとうのことだったら、ややこしい問題になるのは必死だった。生徒間ではたまに聞くことで、密かに中絶費用の捻出のためのカンパ箱が廻ってきたりはするが、学校側に知られたとなると、”堕ろす”だけではすまないだろうと思われた。
『ジリリリ』
待ち兼ねた終業のベルが鳴った。きょうは土曜日なので、たいていの生徒はベルと同時に鞄を机に上げ帰り支度を始めたが、良次と他に七、八人の者は、かたずけることはなにもせず、静かにそっと廊下に出て足早に事務室のある本館へ急いだ。クラスの四分の三の生徒が就職ということがあって、進学組の生徒には自然と静かにことを進めようという雰囲気ができあがっていた。
掲示板の前には既に推薦者名簿が張り出されているようで、他科の生徒が群がっており、それぞれが真剣な表情で見入っていた。落胆ありありの顔、静かにほくそ笑んでいる顔、苦笑いを浮かべ、やっぱりだめかといった顔、そこには高校生なりの悲喜交々の人生があった。
群れの後ろから背伸びをして、名簿の左端のほうを見やった。なにか催しものがあって各科順番に並べられると、電気科はだいたいが一番後ろになるのが通例であった。だがいくら見ても、良次の名前は見当たらなかった。
(はあー、やっぱりな)
念のためと思い、視線を右端に移していくと、なんと右から二番目のところに良次の名前がしっかり書かれてあった。
「やったー!」
思わず声を張り上げてしまい、周りからジロッと見られて良次は首をすくめた。よくよく見ると、電気科の知った生徒の名前はあちこちに散らばっており、どうやら受験する大学ごとに名前を寄せたらしかった。
喜びで一人舞い上がっていると、後ろからポンと肩を叩く者があった。
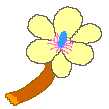
「よう、受かったなあ」
腐った顔をした青柳だった。
「ああ、まぐれだよ」
自分のことしか頭になく、青柳の名前を捜すことなどしなかったので、再度名簿を右端から追ってみた。
「ないよ」
青柳はボソッと、元気のなさの象徴のような言葉で言った。青柳の表情を見たときから、そのような気がしていた。
「そうか、残念だったなあ。ま、おまえの頭だったら一般試験でも受かるさ」
学内選抜に受かった人間が、落ちた人間に向かってなにを言おうとなぐさめにはならないだろうとは思ったが、その場凌ぎにありきたりのことを言った。
「ふん、だったら最初からここに名前が載ってるさ」
(んっ、やぶへびだったか)
いつもなら負けずに減らず口をたたく良次だが、言い返す立場にはなかった。
「はは、気にすんなよ」
青柳は肩をポンポン叩きながら、逆に良次をなぐさめてきた。なにを話題をしたらいいのか言葉が出てこず、あれこれ考えて末に明日のことを訊いた。
「明日の模擬テスト、受けるんだろう?」
「ああ、いくつもりさ。おまえはもう必要ないだろう」
「いや、推薦入学だって面接があるし、小論文もあるからな。いくさ」
「無理すんなよ。もう気分はぶらぶらってとこだろう」
これから先、推薦入学の試験日までの間、よほどのミスでもしない限り大学へのフリーパスを入手したも同じだった。良次はさっき与田から聞いたことを思い出し、青柳を窓際のほうへ引っ張っていって尋ねた。
「クラスの奴から聞いたんだけどさ。おまえ彼女これにしたんだって?」
与田がやったと同じ仕草をとった。
「ふ、早いな。ま、俺の問題だからな、どうでもいいじゃないか」
青柳は相当気分を悪くしたと見え、ふてくされた態度で電気科の別棟のほうへいってしまった。普段の青柳ならざっくばらんに、おもしろおかしく話して聞かせるところだが、やはり今はそんな気分ではないらしかった。
青柳のあとを追いかけて教室に戻るのもいやだったので、何度も自分の名前に見入っていると、また後ろから肩を叩く者があった。
「よかったわね、おめでとう」
ニコニコしながら祝いの言葉をかけてくれたのは、担任の井上だった。
「あ、どうも」
「今ね、会議のときのことを聞いたら、滝田さんはギリギリだったらしいわよ。法学部受験ってことで、推薦してやろうってことになったらしいわ」
「そうなんですか」
「我がS工業から初の法学部進学なんですからね。頑張ってよ、じゃあね」
「はい」
良次は思わず直立不動をして、職員室に向かう井上を見送った。
やはりそうだった。苦しいだろうとは思っていたが、工学部希望でないことが他の生徒より目立つことになり、それが幸いしてのことだった。電気に見切りをつけて法学部進学を決めたときは、母や兄からはなんのために工業高校に入ったんだ、などとさんざん言われて迷いに迷ったが、今やっとそれが正解だったと自信を持つことができた。
善は急げとばかりに学校を出た。最初に伝えたかったのはもちろん理沙で、きょうはK公園の端にあるコーヒー専門の喫茶店の近くで待ち合わせることになっていた。受かればその店で、サンドイッチなどをつまみながら一番高いコーヒーで祝杯をあげることになっており、落ちればパン屋で菓子パンと缶コーヒーを買い込み、公園のベンチで惨めたらっしく残念会をやる段取りになっていた。

|

|

|

|

|