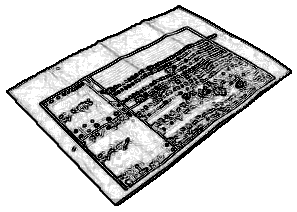
2 出生の秘密
「ほんとにご迷惑をかけて申し訳ありませんでした。二度とこのようなことはさせないようにしますので。さ、あなたもぼおっーとしてないで謝まりなさい」
おばは有無を言わさず、後頭部を押さえたかと思うと無理矢理頭を下げさせた。
香奈子はうつむき放しだったので、売り場責任者の表情は見えはしなかったものの、どんな顔つきで香奈子を見ているかおよその検討はついた。
「まだ若いんだし、こんなことでいじけることなく、これからはきちんと買い物をしてってくださいよ」
警備担当者の接し方には顔を鬼のようにし怒鳴り声を張り上げてくる威圧的なタイプと、私は教育者でございといった顔をして延々と説教をぶってくるとタイプとの二種類がいる。きょうのは典型的な後者に属する人種だった。
スーパーやディスカウントショップでは前者の型が多かったが、デパートとなると案外やさしいおじさんが多いとは、もっぱら仲間内輪での話しだ。
「小遣いはきちんと持たせているというのに、ほんとに困った子です。なにからなにまでよけいなお気遣いをしていただきましてありがとうございました」
おばが爪先を外に向けたとたんに香奈子も身体を開いてドアのノブに手をかける。それをおばは腰元を掴んでもう一度中に向けさせ、礼をしながら通路に出た。おばの世話になるのは、これで三度めだった。
腰に回った手は離れることなく、ひっつくようにしながらデパートの中を歩いていく。エレベーターに乗るときにはおばの手を振りほどこうとしたが、しっかり掴み返してくる。それでいて一言も口をきいてくることはなかった。
車に乗ってからもおばは脇見もせず、もくもくとハンドルを握っている。西道路のトンネルに入り、数分で抜けて自宅近くの数百メーター手前まできたときだ。
「このへんでいいでしょ。あまり近すぎて見つかったりすると大変だしね」
「別にいいわ、今さら。家の前までやって」
「だったら自分で言いなさい。だいたいにしてそういうことを言うんだったら、始めから私の電話番号を教えなければいいでしょう。私だって好きでいったわけじゃないの。無理して仕事の時間を割いていってるのよ」
これまでにはないおばの様子に、香奈子は驚いておばを振り向いた。「勘違いしないでよ。香奈ちゃんのために親に秘密にしとくんじゃないの。これ以上二人によけいな心労をかけたくないからよ。最近お父さんが血圧高いのは知ってるでしょ」
「医者の不養生なのよ」
「そうやっていつまでも憎まれ口を叩いてるといいわ。兄が香奈ちゃんの能力以上のものを押しつけて厳しくし過ぎたところは認めるわよ」
「だったらとやかく言わなくたっていいじゃない。人にはそれぞれ向き不向きっていうのがあるんだから」
「おじいちゃんの代から医者だったし、ひとり娘の香奈ちゃんに跡を継いでほしいってことはあるでしょう。だから同情はするわ。でもね、それだけじゃないわよ。結婚して家庭に入るのを悪いと言うつもりはないけど、それで人生がすべてうまくいくってものでもないわ。手に職をつけておいた方がいいに越したことはないでしょう。実際お姉さんだってそうしてきたし、私だって自分で店をもってがんばってるでしょう」
「お母さんはお母さん。私は私よ」
「そういうこと。もう十七なんだからわかって当たり前だけど。さ、降りて」
おばは身体を伸ばすと助手席のドアを自分で開け、香奈子を放り出すようにして出した。
「おばちゃん、冷たくなった」
香奈子は恨めしそうに窓越しにおばを見た。
「何度も同じことをやって、口でどうこういったって始まらないでしょう。高校を退学になって他の通信教育や定時制にいくつもりはないようだし、かといって働きもせずにぶらぶらしてる姪っ子をいつまでも甘やかしておくわけにはいかないわ。それじゃね」
と発進しかかったところで再度車を止め、一度は閉めた助手席のパワーウィンドウをまた開けた。「香奈ちゃんに一つ話しておくことがあるわ。二人にはどんなことがあっても教えてくれるなって言われてることなんだけど」
そう言ったきり、前を見据えたまま動かなくなった。
「なによ、もったいぶらないで言ってよ」
「香奈ちゃんはお父さんとお母さんの子供じゃないの。赤ちゃんのとき、養女にもらわれてきたの。覚えてる?」
「な、なに言ってんの。そんなこと言って脅かそうとしたってだめよ」
「二人のあいだにはなかなか子供ができなくてね。友人で産婦人科をやってる人がいるのね。そこに妊娠した若い子がやってきて、中絶するには遅すぎるということで、やむを得ず子供を産んだわけ。その子を二人がもらってきて育てたのよ。それが誰か、わかるわね」
「嘘よ。そんな作り話しで私に恩着せがましい気持ちにさせようとでもいうなら逆効果よ」
と言うなり、屋根をへこむほどに叩いた。
「確かお姉さんが三十七、八のときに産んだことになってるはずよ。香奈ちゃんの生年月日から逆算すればわかるでしょう。同い年の二人が研修医のときに知り合って二十六で結婚してから、十年以上も子供をつくらないなんておかしいと思わない。なにより初産にしてはお姉さんが高齢過ぎると思わない」
「高齢出産する人なんて大勢いるわ」
そっぽを向きはしたが、顔は青ざめていた。
「生まれてすぐだったらしいわ。何日かしてから教えてもらって見にいったけどすごくかわいかったわよ。それがどこでどう間違っちゃったのかしらね」
「フン・・・」
「少しでも自分を見つめ直すきっかけになればと思って話しただけよ。どうしても信じたくないというなら、戸籍を見てみるといいわよ」
ドアに背中越しに寄りかかっていたのが身体をひるがえし、窓越しにのぞき込んでくる。
「戸籍に書いてあるものなの?」
「そりゃ書いてあるわ。誰の子供が誰の養女になったってことがね」
今度はドアを開けて助手席に乗り込んできた。
「それって区役所で出してくれるんでしょう。このままもどって区役所まで乗せてって」
「きょうはこの時間だから閉まってるわよ。気になるんだったら明日朝早くいって見たらいいわ」
香奈子がうなだれたまま車から降りようとするのを、おばが腕をとってシートに引き戻した。「血が繋がっていようがいまいが、香奈ちゃんはお父さんとお母さんの子供ということに変わりはないの。私がおばであることもよ。いいわね」
返事することもなく、腕を振りほどき車から出た。とぼとぼ歩いていくのをおばはしばらく車を止めたまま見ていたが、その場でUターンするときた道路を走り去っていった。
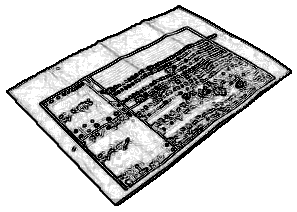
翌朝香奈子は九時前には青葉区役所の玄関前に立ち、ドアが開くと井の一番で戸籍謄本の申請をした。
呼び出しを受けると手数料を払うのももどかしく謄本を開き、“杉本香奈子”の欄を見る。くり返し見たが、どこにも“養女”の二文字は書いてなかった。父・母の欄にもまちがいなく両親の氏名が記載されてあった。
それを右手に握りしめたまま、香奈子は外に飛び出した。あらん限りの全速力でおばが経営するブティックに向かって走ったが、店にはシャッターが下りたままで開店までにはまだ間があった。今度は百メートルほど離れたおばが借りている月極駐車場まで走る。するとちょうどおばが着いたところだった。
「おばちゃん、どうしてあんな嘘ついたの。言っていいことと悪いことがあるでしょ」
目の前に戸籍謄本を突き出す。
「慌てないで落ち着いて話してよ」
「見ればわかるわよ。おばちゃんだけは信用してたのに。裏切り者!」
苦笑いを浮かべながらおもむろに謄本を手にし、開いて見ていくうちに穏やかな表情は怪訝な様相に変わった。
「ふーん、ほんとね。戸籍を見る限り養女の痕跡はないわね」
深い溜息をついてシートに身を預けた。
「この期に及んでとぼけるつもり。お詫びの印にこの車でも譲ってもらおうかしら」
「まだ免許もないくせになに言ってるの。とにかくこっちに座んなさい」
「いいわよ。言い訳だったらいくらでも聞いてあげる」
香奈子は額の汗をハンカチで拭き取りながら助手席の側に廻り、車に乗り込んだ。
「私も香奈ちゃんたちの戸籍を見るのは初めてなんだけど、香奈ちゃんを養女にしたのは生まれて数日のうちなの。それからすぐ別のアパートに引っ越して、数年経ってから実家にもどっておじいちゃんの跡を継いで開業したのよ」
「そんなこと関係ないでしょ。いくらおばちゃんだってこれ以上・・・」
「黙って聞きなさい。出生届けは産まれてから二週間以内に出さないといけないんだけど、自分たちの実子として届け出ればそれで済むことなのよ。法律で禁止されてはいるんだけど、お父さんとお母さんはその方法をとったんだと思うわ」
「どうしてそんな手の込んだことする必要があるの?」
口を尖らせて聞いた。
「そりゃあとあと香奈ちゃんにわからないようにするためよ。いずれ戸籍を見たらわかるだろうと思って言ったんだけど、とんでもないことを話してしまったのかもしれないわね」
ハンドルにもたれかかるようにしながら自嘲気味に笑った。
「でも、なんかおかしい」
身体を真横にしておばを睨む。
「こう言ったらなんだけど、香奈ちゃんはお父さんにもお母さんにも似なくて美人でしょう。お母さんには内緒よ」
香奈子の強ばった顔が幾分くずれる。「香奈ちゃんの血液型はなによ?」
「小学生のときに検査しただけだからよく覚えてないけど、A型かAB型だったと思うわ」
「女の子なら血液型占いなんかこだわるのに、あなたはつくづく変わった子ね。血がつながってるわけじゃないのに私に似たのかしら」
「おばちゃんもいろいろ悪いことしたの?」
「香奈ちゃんほどじゃないけどね」
二人は顔を見合わせて笑った。
「兄は確かB型だったけど、お姉さんのは聞いたことがないわね。血液型の遺伝に関してはよく知らないけど、とりあえず自分の血液型を調べて、それとなくお母さんにも聞いて血液型から判断する方法があるわね。それでなければ私に聞いたことを話してもらってかまわないから直に確かめるといいわ。なんだったら四人いっしょのところで私から話してもかまわないわよ」
「・・・・・・・」
「これまで私が香奈ちゃんに嘘をついたことがある? 問題を起こしたお店や警察から連絡があれば飛んでいってるし、そのことをお父さんやお母さんに告げ口したことがあった」
香奈子は押し黙ったまま首を横に振った。「お父さんとお母さんに直接問いただすのが怖いんだったら、自分で時間をかけて納得いくように調べてみなさい」
「うん」
「それとね、血液型を調べるんだったら保健所にいってエイズ検査をやってみたらどう? そのときに血液型もわかるはずだから。かなり男遊びもやってるんでしょう」
「知らない」
「困った子ね、私の若いときにそっくりなんだから。大丈夫よ、どんなことがあってもおばちゃんが守ってあげる」
そう言って横から香奈子を膝元に抱き寄せると、身体が堰を切ったように震えだした。
香奈子は家にもどると父の書斎に入り、百科事典やむずかしい医学書を片っ端から開いていった。
探すこと一時間あまり、やっと目的とする書物が見つかった。それによれば子がAかABの場合は両親の一方がBとすれば、もう一方はAかABでなければならない。つまり母が香奈子と同じであれば問題はなかった。
どういう風に母に尋ねたものか考えあぐねていると、香奈子が小学低学年のとき、母が献血してきたことを話していたのを思い出した。
「そうだ、献血手帳だわ」
母の書斎といえる部屋はなかったが、和室がその代わりになっていた。引き出しやタンスを手当たり次第に探してみるが、献血手帳は見つからなかった。
あきらめかけたところでやはり献血をしたことのある同級生が、献血するときや事故などに遭ったときのために献血手帳は肌身離さずもっていた方がいい、と語っていたのを思い出した。
居間にとって返し母のハンドバッグを隅から隅まで調べる。だが、献血手帳はなかった。まさかとは思いながら裏地の後ろ側に入れてないか、小物を全部出して指先でまさぐっていくとそのまさかだった。
震える手で手帳を開くと、血液型の項目には“O型”と記されてあった。一瞬頭が真っ白になった。
とそのとき、医院との通路になっている廊下の方から足音が聞こえてくる。反射的に壁時計を見ると十二時を過ぎていた。香奈子は慌てて手帳と小物をハンドバッグに入れ置いてあった場所にもどした。
「なにをやってるの。こそ泥みたいな真似をやって恥ずかしくないの」
香奈子が自分の部屋にいこうとするのを、母は上着を掴んで離さなかった。「いったいいつになったら直るのよ。親が元気なうちはいいけど、いつかはあなた独りでやっていかなくちゃならないのよ」
片手で頭を支えるようにしながらテーブルにもたれかかるのだった。小児科医の母は既に五十を過ぎていたが、いつもならきびきびして年を感じさせない。それがきょうは白衣姿の背中がやけに小さく見えた。
「どうした? 今度は何をやったんだ」
父ももどってきた。母はなにも言わなかったが、留め金が外れたままのハンドバッグはすぐ父の目にも入った。
「馬鹿者!」
と言い終わらないうちに香奈子の頬に平手打ちが見舞いソファにはじき飛ばされたが、どういうわけかその父も後ろに仰け反って倒れた。
「まあ、大変! 香奈子、座布団をもってきて」
頬の痛さも忘れ、言われるままに飛んで和室から座布団をもってくると、父の頭の下にそっと入れた。「救急車を呼んでちょうだい」
と言うなり、母は医院に向かって走り出していた。
もどってきたときには、その手には注射器があった。
「血圧が高過ぎるせいなの?」
「あなたには心配させたくないから黙ってたけど、心臓の病気よ。激しい運動とか興奮するのはよくないの。救急車は呼んでくれた」
「うん、すぐくるって」
まもなくサイレンの音が聞こえ、救急隊員がストレッチャーを引っ張りながら上がってきた。
「狭心症です。T大付属病院の心臓外科の斉藤教授が主治医になってますので、そちらまでお願いします」
「承知しました」
「お母さんは患者さんがいるでしょう。私がいくわ」
「そうね。ここが終わったらすぐに駆けつけるからそのあいだお願いね」
引き出しから保険証と、さっきのハンドバッグから財布を取り出すと、そのまま香奈子の手に渡した。
ストレッチャーに乗せられた父は顔を歪め、目はつぶったままで意識は朦朧としているようすだ。救急車に乗せられ香奈子もあとから乗る。大きなドアが上から閉まりかけたとき、
「お母さん、ありがと」
母は足を半歩踏み出し問い返す表情になったが、ドアは閉まり車は動きだした。
酸素マスクを被せられてからは楽になったようで、表情はだいぶ和らいでいた。気がつけばふさふさしていた頭の黒髪は、だいぶ薄くなっている。柔道五段のがっしり体格もいつのまにか筋肉が落ちていた。
「お父さん。私ね、来月からおばちゃんのところで働くことにしたの。聞こえる?」
それまでつぶったままの瞼がかすかに動いた。

|

|

|

|

|